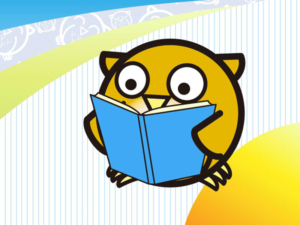天皇誕生日

天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。こうして国民が陛下のお誕生日をお祝いする、というのはなぜなのでしょうか。誕生日のお祝いというのは家族とか、親しい人、大切な人に対してです。つまり天皇陛下というのは国民にとって、大切な人と考えている、ということになります。この機会に、なぜ天皇というご存在が大切なのかを考えてみるのもよい機会です。世界には王国がいくつもありますが、どの王朝も交代があり、日本の皇室が世界で一番長い家系であることが知られています。二千年以上の家系を誇っているのは、日本だけでなく、アラビア諸国の中には、ムハンマドの家系であることを大切にしている国もあります。家系というのは、「家」という概念が前提ですが、これは誰もがもつ「家族」という概念の延長と考えられます。家族という概念は人間なら誰もがもつのですが、動物にも親子の概念をもつものがたくさんあります。進化の段階で、どこから親子または家族という概念が発生したのかは知りませんが、子育ては種の保存にとって重要であることは間違いありません。家族が発展した共同体という社会制度は、日本の場合、弥生時代からであろう、という推定が定説のようです。環濠集落という住居形態が発掘されており、稲作という生産形態がそれに向いていたと思われています。共同体という社会制度は農耕社会でなくとも発生し、狩猟文化であれば、共同で大きな獲物を得ることがあり、リーダーの発生も推定されます。こうした共同生活に不可欠なのがコミュニケーションであり、言語の発達が関係している、というのも定説です。共同体には、当然リーダーが不可欠であり、それが他の共同体との闘争の際には効果を発揮します。それが王の起源でもあり、日本では豪族と呼ばれた集団となりました。各地域の豪族間の闘争もあり、とくに統一的な社会を形成する際の闘争は必然であったと思われます。その結果、最終的に統一した豪族が天皇家の祖先であったというのは正しい理解と思います。しかし諸豪族がすべて消滅したわけではなく、臣下になったり、細々と続いたりするのは自然なことで、それが「家」という概念として補強されていったのが日本の文化です。この家という概念が現実化したのが、墓であり、戸籍や家系図といえます。この墓という文化は宗教と不可分です。死生観と不可分であり、「死んだらおしまい」という唯物論的な死生観もありえますが、「死んでも魂が残る」という死生観が宗教の起源ともいえます。魂が住む世界が「あの世」ですから、墓はその2つの世界をつなぐ入口ということになります。現在の日本は、墓をもたない、宗教をもたない、戸籍は不要、と思う思想の人が増えているようです。しかし、反対の考え方の人もいます。これを法律などで規制することは問題があります。天皇陛下を尊崇する人もいて、尊崇しない人もいます。「天皇制」を無くせ、という主張は「多様性」を主張することと矛盾します。自由社会においては、いろいろな人がいて、いろいろな制度があります。文化は長い間をかけて成立したものなので、改革には慎重であるべきと思います。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |