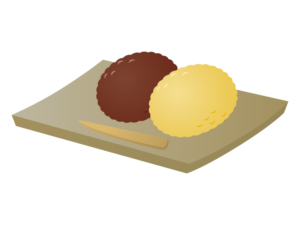彼岸の中日
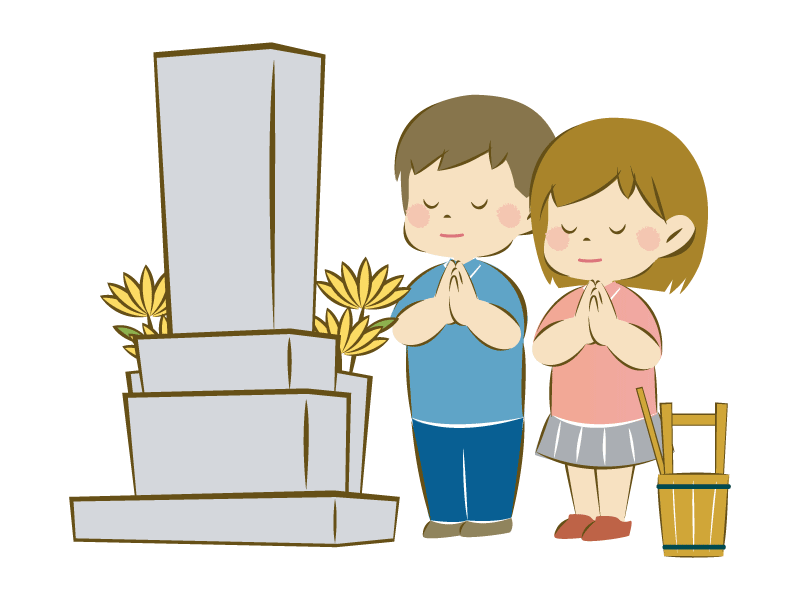
彼岸は中日を真ん中に「入り」と「明け」を含めて7日間あります。現在は「〇〇の日」のような1日かぎりの行事が圧倒的に多いのですが、昔は祭りといえば3日間あるのが普通でした。それは海外でも同じだったようで、わくわくする行事は長く楽しみたいのが自然な感情でしょう。そして現代のように楽しみが多くなかったので、行事が娯楽になっていた面も否定できません。そもそも宗教も現代で考える思想的な側面やイデオロギーとの関係は薄く、ほとんどの人々にとって、生活習慣の1つに過ぎなかったと思われます。
お彼岸も根本には仏教の思想がありますが、一般庶民は漠然と理解していて、今でも「お墓参りの日」と思っている人がほとんどでしょう。「彼岸」という言葉の語源はサンスクリット語の「paramita(パーラミタ)」で、日本では音写語で「波羅蜜多(はらみた)」と呼んでいます。「般若波羅蜜多(はんにゃはらみた)」というよく聞く仏教用語でおなじみのあの「はらみた」です。少しだけ言語的な意味を解説すると、波羅(はら)は、サンスクリット語で、パーラムという言葉を音写した字です。波羅は「あちらの岸、彼岸(ひがん)」という意味です。蜜多は、サンスクリット語で、イターという言葉を音写した字です。蜜多は「~に到る」という意味です。波羅蜜多のパーラム・イターが、パーラムイターとなり、ムイという音がミに変化してパーラミターとなります。それが漢訳で「波羅蜜多」となり、それを日本語風に読んで「はらみった」となったわけです。言語が漢語と日本語の2つを渡ってきたのですが、音写語のため、原語の音に近いものとなっています。しかし漢字の意味は関係がないので、いくら眺めても意味はわかりません。こういう原語の音写語は経典に多いので、漢字ばかりのお経を読んでもさっぱりわからないことが多いのは当然です。もっとも全部が音写語ではないので、ところどころ意味がわかります。それで余計、不思議な感じがするのかもしれません。波羅蜜多と波羅蜜はほぼ同じ意味と考えられていて、最も深奥の修行(彼岸行)のことを意味します。その漢訳は「至彼岸(とうひがん)=彼岸に至る」になることから、「彼岸」は「悟りの世界(浄土の世界)へと辿り着く」という意味と解釈されています。つまり、お彼岸にお墓参りをすることも「修行」の1つなのです。
「修行」というと、座禅を組んだり、滝に打たれる、というような厳しいものを連想しがちですが、仏教ではそうした修行だけでなく、普段よくするお賽銭や喜捨などの行為も修行の1つなのです。専門職としての僧や行者は、厳しい修行をするわけですが、普通の信者には義務化されていません。易しい修行が生活習慣の中に採り入れられていったわけです。なお、仏典の中では修行と呼ぶことは少なく、「行(ぎょう, carita)」とのみ呼んでいます。そして特に厳しく苦しい行を苦行(くぎょう)、特別重要で中心的な修行を正行(しょうぎょう)、補助的な修行を助行(じょぎょう)と呼んでいます。あまり深く踏み込むと心理的な負担になりますから、まずは気軽にお彼岸を迎えられてはいかがでしょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |