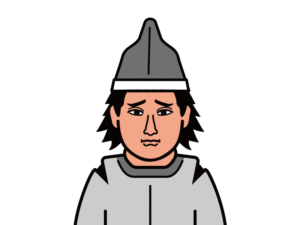奥の細道

元禄2年(1689)弥生3月27日(旧暦) 松尾芭蕉が弟子の河合曾良とともに『奥の細道』の旅に出発しました。おくのほそ道(奥の細道)は、芭蕉が崇拝する西行の500回忌にあたる1689年(元禄2年)に、門人の河合曾良を伴って江戸を発って、奥州、北陸道を巡った紀行文です。全行程約600里(2400キロメートル)、日数約150日間で東北・北陸を巡って、元禄4年(1691年)に江戸に帰りました。西行500回忌の記念すべき年に、東北各地に点在する歌枕や古跡を訪ねることが、最大の目的の旅であったのです。
西行といい、芭蕉といい、全国を旅しながら、和歌や俳句を詠むのは多くの人の憧れでもあります。元禄2年春 芭蕉は旅立ちの準備をすすめ、隅田川のほとりにあった芭蕉庵を引き払いました。その時の句が「草の戸も 住み替はる代よぞ 雛の家」です。3月27日明け方、採荼庵(さいとあん)より舟に乗って出立し、千住大橋付近で船を下りて詠む。「行く春や 鳥啼なき魚の 目は泪」。この句は春を惜しむ句として有名です。この句の意味上での区切りは【鳥啼き魚の 目に泪】ではなく、【鳥啼き 魚の目に泪】となります。「鳥啼き魚」という魚がいるわけではないので注意が必要です。うっかりそういう魚がいるのかと検索してしまいそうです。現代語訳すると「春が過ぎ去ろうとしているところに、旅立つ別れを惜しんでいたら、鳥たちは悲しそうに鳴き、水の中の魚も涙をためているではないか。より悲しみが沸き上がってくる。」(https://haiku-textbook.com/yukuharuya/)となり、説明すると長くなることを凝縮して五七五にまとめるのが句の醍醐味です。
現代の欧米でもHAIKUという短い詞が流行っています。ほとんどは韻律を含んでいませんが、心境を短くまとめることで、より深い感動を与えるという精神は継承されていて、日本の美意識として尊敬されています。千住大橋から四日目の4月1日下野国日光(栃木県日光市)に着き読んだのが「あらたふと 青葉若葉の 日の光」です。春も過ぎて青葉が目に染みるような季節になったことがわかります。木々の間から、木漏れ日(こもれび)がさしている美しい情景が目に浮かびます。「あらたふと」とは「なんととおといことか」という意味で、この一言で、日光東照宮への尊崇の気持ちが表現されています。現代人が観光気分で東照宮を見るのと違い、芭蕉は江戸時代の人ですから、江戸幕府と家康公、家光公への尊敬の気持ちが強かったに相違ありません。奥の細道は、句の美しさもさることながら、こうした時代背景や芭蕉の気持ちを想像しながら、味わうのも楽しいものです。実際に現地を旅すれば、なお一層、その思いは伝わってくると思います。その気持ちは芭蕉が西行に憧れて旅した気持ちと通ずるものがあります。
現代の私たちも、てらうことなく、西行や芭蕉に憧れて、旅をして、和歌や句を読んでみるのも、また楽しい旅になると思います。それが残って後世の人から評価されるかどうか、などどうでもよいことです。自分の思い出のためだけに、記録しておくのも楽しい思い出につながると思います。写真や動画に頼らない文の世界がそこにあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |