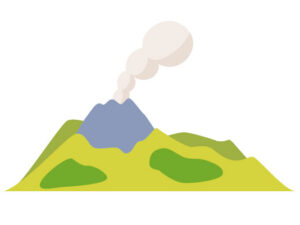物部守屋と丁未の乱
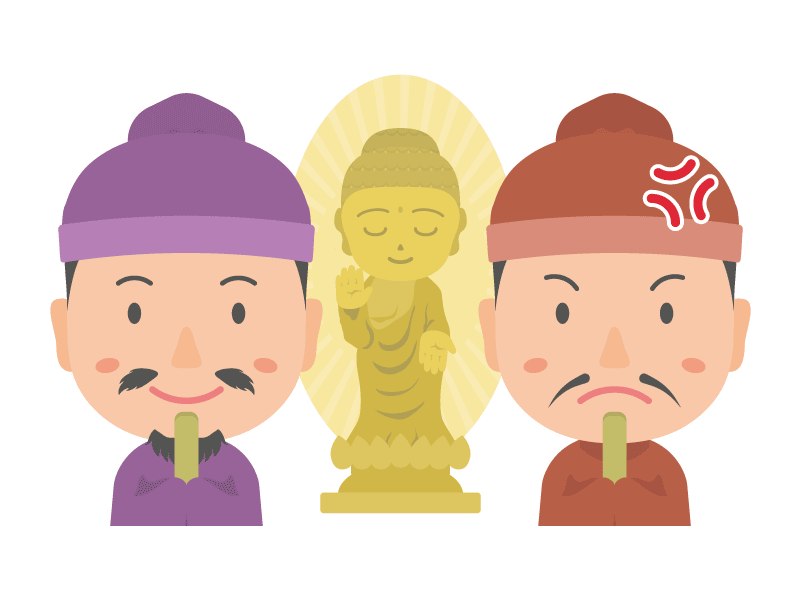
物部氏は日本史上、反逆者扱いになっていますが、それは仏教を信奉した蘇我氏が政権を取り、聖徳太子が仏教を広めていったことが正史とされているためです。
以下、wikipediaのまとめを引用します。「物部氏は日本に伝来した仏教に対しては強硬な廃仏派で、崇仏派の蘇我氏と対立していました。敏達天皇元年(572)、敏達天皇の即位に伴い、守屋は大連に任じられました。敏達天皇14年(585)、病になった大臣・蘇我馬子は敏達天皇に奏上して仏法を信奉する許可を求めたところ、天皇はこれを許可したが、この頃から疫病が流行しだしました。守屋と中臣勝海(中臣氏は神祇を祭る氏族)は蕃神(異国の神)を信奉したために疫病が起きたと奏上し、これの禁止を求めました。天皇は仏法を止めるよう詔しました。守屋は自ら寺に赴き、胡床に座り、仏塔を破壊し、仏殿を焼き、仏像を海に投げ込ませ、馬子や司馬達等ら仏法信者を面罵した上で、達等の娘善信尼、およびその弟子の恵善尼・禅蔵尼ら3人の尼を捕らえ、衣を剥ぎとって全裸にして、海石榴市(つばいち/つばきいち、現在の奈良県桜井市)の駅舎へ連行し、群衆の目前で鞭打ち暴力によって仏教を弾圧する暴虐さを見せました。しかし、疫病は更に激しくなり、ついに天皇も病に伏しました。馬子は自らの病が癒えず、再び仏法の許可を奏上しました。天皇は馬子に限り許しました。馬子は三尼を崇拝し、寺を営みました。ほどなくして、天皇は崩御しました。殯宮で葬儀が行われ、馬子は佩刀して誄言(しのびごと)を奉りました。守屋は「猟箭がつきたった雀鳥のようだ」と笑いました。守屋が身を震わせて誄言を奉ると、馬子は「鈴をつければよく鳴るであろう」と笑いました。」敏達天皇の次には馬子の推す用明天皇(欽明天皇の子、母は馬子の妹)が即位した。守屋は敏達天皇の異母弟・穴穂部皇子と結んだ。用明天皇2年4月2日(587年)、用明天皇は病になり、三宝(仏法)を信奉したいと欲し、群臣に議するよう詔しました。守屋と中臣勝海は「国神に背いて他神を敬うなど、聞いたことがない」と反対し、守屋は朝廷を去り、別宮のある阿都(河内国)へ退き、味方を募りました。排仏派の中臣勝海は彦人皇子と竹田皇子(馬子派の皇子)の像を作り呪詛しました。しかし彦人皇子の邸へ行き帰服を誓ったのですが、その帰路、舎人迹見赤檮が中臣勝海を斬ってしまいます。そして用明天皇は崩御し、守屋は穴穂部皇子を皇位につけようと図ったのですが、馬子は穴穂部皇子の宮を包囲して誅殺した。翌日、宅部皇子を誅しました。馬子は群臣にはかり、守屋を滅ぼすことを決めます。守屋は一族を集めて稲城を築き守りを固めました。その軍は強盛で、厩戸皇子は仏法の加護を得ようと白膠の木を切り、四天王の像をつくり、戦勝を祈願して、勝利すれば仏塔を作り仏法の弘通に努めます。守屋の軍は敗北して逃げ散り、守屋の一族は尽く殺害されました。厩戸皇子は摂津国(大阪市天王寺区)に四天王寺を建立しました。物部氏の領地奴隷の半分は馬子のものになりました。半分は四天王寺へ寄進されました。こうして仏教は国教となっていきました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |