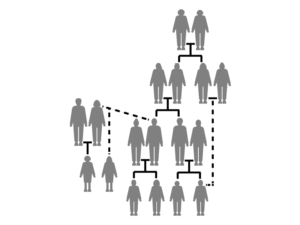女子断髪禁止令
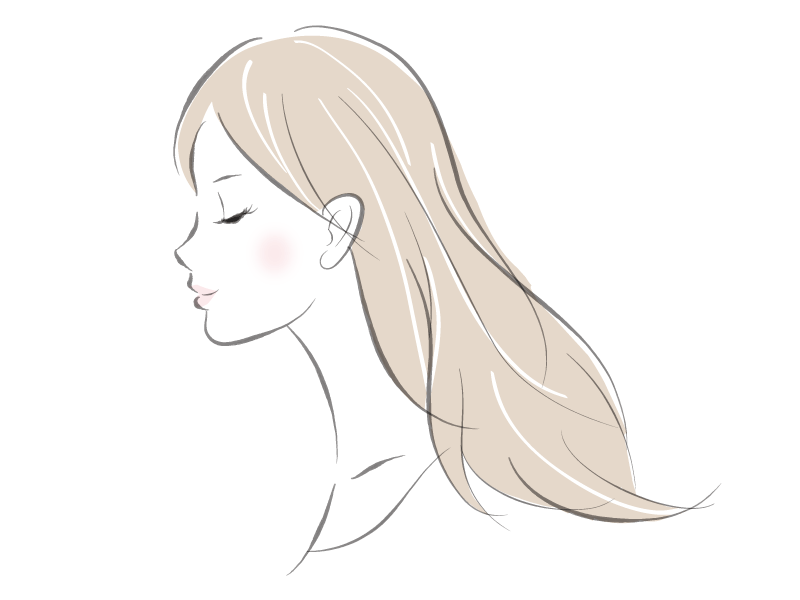
明治5年(1872)4月5日(旧暦)、東京府は男女の区別が判然としない髪型は禁止すべきという考えから女性はみだりに髪を切ってはいけないという「女子断髪禁止令」(東京府達32号)を布告しました。このことはあまり知られていません。東京府が太政官に「婦人断髪ノ儀ニ付伺」と許可を求めました。当時、日本髪を結うのに鬢付け油が使われていました。結髪もさることながら洗髪も時間がかかり面倒でした。それに猛反発して長髪文化の古い価値観と戦った女性たちがいました。それが現在の「ヘアカットの日」につながっています。
この混乱のそもそもの原因は1年前の明治4年(1871)に、明治政府が太政官布告により、マゲを切り刀を差すこと辞める「散髪、制服、略服、礼服ノ外、脱刀モ自今勝手タルベシ」という「散髪脱刀令」を布告していることにあります。この散髪脱刀令を「女性も断髪せねばならない」とらえた女性の間で断髪が流行し、男性のような短髪にしてしまう若者が増えていきました。しかし、当時は「黒い長髪こそが女性らしい美しい姿である」という価値観が広く浸透しており、世論は女性が短髪にすることに猛反発しました。そこで当時の東京府は「婦女子のザンギリと男装はひっきょう『散髪の儀は勝手たるべし』」と、女性に対して散髪脱刀令の趣旨のとり違えを正し、女性は従前のとおりにせよという「女子断髪禁止令」の布告に至ったというわけです。
髪型を巡る議論は今でも、男子学生の坊主頭の強制などが話題になります。女子学生の長髪を制限している学校もあります。「服装の乱れは心の乱れ」という論理性がまったくない標語がよく使われました。それに対抗する論理が「表現の自由」という大げさな議論になっているのもおかしな話です。長髪という生活習慣が憲法問題というのは論理の飛躍でしょう。「黒い長髪こそが女性らしい美しい姿であるという価値観」はなくなったかというと、一部でも今も続いているので、新しい、古いということでもなさそうです。
髪型の男女差は日本の伝統ではなく、世界を見ても普遍的に存在します。ヘルメットの着用には短髪が便利ですが、長髪をまとめて着用する女性も多いですし、働きやすいということから、こういう髪をまとめるスタイルも普通にあります。男性の場合、長髪もいますが、職業的にアーティスト系に限定され、それでも、最近はちょんまげスタイルが流行っていて、短いことが当たり前のようになっています。政治家や公務員で長髪の男性は稀有でしょう。つまり、髪型は性別、職業、思想などを示すエンブレム(表象)となっているわけです。
こうした文化的通念は政治的な意図で変えることはなかなか難しいものです。歴史的には、反対派の女性達が「婦人束髪会」を結成し、従来の「結髪(日本髪)」が如何に手間であり、女性の金銭的な負担や使用していた植物油の衛生面の懸念を日本政府に訴えました。そして彼女らは切ってはいけないのならと、結髪(日本髪)に代わって西洋の影響を受けた簡易的な「束髪」を流行させ、次第に結髪(日本髪)文化は姿を消していきました。今、日本髪の人が出てきているのは皮肉です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |