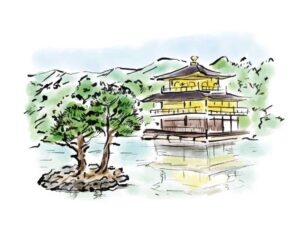阿弖流為

阿弖流為(あてるい)は、8世紀末から9世紀初頭にかけて東北地方で活躍した蝦夷(えみし)の指導者です。彼は大和朝廷の支配に抵抗し、蝦夷の人々を率いて戦いました。
蝦夷とアイヌは、しばしば同じように扱われることがありますが、実際には異なる歴史的背景や文化を持っています。ただし、蝦夷の中には、アイヌとつながりの深い人々もいました。歴史の中で、東北地方から北海道に移住した人も多く、文化的な影響を受けている部分もあります。しかし、「蝦夷=アイヌ」というわけではありません。DNAによる研究によると、蝦夷は縄文人の血を受け継いでいる人が多く、アイヌも縄文人の特徴を強く持っています。DNAレベルでは共通点があるものの、歴史的な背景や文化は異なると考えられます。8世紀の東北地方には朝廷の記録では「蝦夷(えみし)」と呼ばれた人々が、現在の岩手や青森を含む地域に暮らしていました。冬が長く、積雪も深いこの地では、中央政権のような稲作を中心とした農耕文化は根づきにくく、代わりに狩猟、漁労、山菜や木の実の採集といった自然資源を活かした生活が営まれていました。彼らは川で鮭を捕らえ、山で獣を追い、季節に寄り添う暮らしを続けていたのです。
歴史に残る蝦夷と朝廷との闘いの最初は巣伏の戦い(789)で、阿弖流為は母禮(もれ)とともに蝦夷軍を率い、征東大使・紀古佐美の軍を撃退し、大勝利を収めました。次が有名な坂上田村麻呂との戦い:です。朝廷は征夷大将軍・坂上田村麻呂を派遣し、蝦夷討伐を強化しました。徳川時代まで続く征夷大将軍の「征夷」とは蝦夷を征伐する、という意味です。延暦21年(802)4月15 日(旧暦)阿弖流爲は坂上田村麻呂に降伏しました。阿弖流為と母禮は、五百余人の仲間を率いて坂上田村麻呂の陣営に自発的に出頭し、降伏の意志を示しました。この事実は朝廷の記録『日本後紀』にも記されており、捕縛ではなく、自らの判断による降伏であったことが明確に記録されています。これは、蝦夷側の指導者が自発的に朝廷に屈した、稀に見る例でした。この降伏の背景には、継戦による疲弊と、それに伴う民の苦境があったと考えられます。戦いを続けることで犠牲が拡大することを避け、共同体を存続させるための選択として、阿弖流為が「剣を置く」ことを選んだという解釈は、現在の研究でも広く支持されています。降伏を受け入れた坂上田村麻呂は、阿弖流為と母禮を都へと護送します。彼は二人の助命を朝廷に嘆願しました。その記録は『日本後紀』や『日本紀略』に記されており、田村麻呂が阿弖流為の武勇と統率力を高く評価していたことがうかがえます。彼は敵将であっても有能な人物として再利用すべきだと考えたのでしょう。しかし阿弖流為たちは坂上田村麻呂の嘆願にもかかわらず、京都で処刑されました。
京都の有名な清水の舞台を降りたところに「アテルイ・モレの碑」があります。清水寺は坂上田村麻呂が創建したといわれているからで、田村麻呂は供養したかったのかもしれません。(https://rekishis.com/210参照)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |