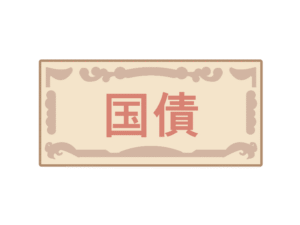小満

今年は5月21日から、二十四節気の1つである小満に入ります。立春から数えて8番目(立春を含む)の節気です。小満とは「植物や動物などのありとあらゆる生き物が次第に成長し、天地に満ち始める頃」という意味です。草木が生い茂り、動物たちも心地良い気候を楽しむ時期とされています。
小満は万物が次第に成長し天地に満ち始める頃で、江戸時代の『暦便覧』では、「万物盈満(えいまん。物事が充分に満ち足りること)すれば草木枝葉繁る」とあります。小満には、秋にまいた麦に穂がつく頃にあたり、その出来具合に「少し満足する」、ひと安心するといった意味もあります。小満とは、元々草花などが生い茂り、生命力に満ちていく様子を指す言葉で、大満足というよりも、ほっとした趣が日本人には好まれるようです。現代では、ひとつ前の二十四節気である立夏と比べると日常生活では使われることがなく、馴染みのない言葉かもしれませんが、感覚としては納得がいくと思われます。
小満の時期は、麦の収穫期に差し掛かる頃です。この時期に手紙や俳句、短歌を書くなら「麦秋(ばくしゅう、むぎあき)」や「麦の秋」などの季語が使われます。秋というと、米が連想されるのですが、それを下敷きにした表現です。麦秋も麦の秋も、いずれも初夏の季語として使われます。古来、日本人の生活に重要な役割を担ってきたのは、米だけではありません。麦も日本人の生活に欠かせないものとして扱われてきました。今では、うどんなど、麺類やパンなどに使われることが多いのですが、昔は麦飯のように主食として食べられていました。
二十四節気には節気を3つに分けた七十二候がありますが、小満の初候は、蚕起食桑(かいこおきてくわをはむ)です。蚕が桑の葉を盛んに食べだす頃という意味です。この時期になると、蚕の食欲が旺盛になり、餌を桑の葉をどんどん食べます。やがて蚕がつむいだ繭が、美しい絹糸になります。少し前まで、日本は絹織物が主たる輸出品でした。
次候は、紅花栄(べにばなさかう)です。紅花の花が咲きほこる頃です。紅花は黄色がかったオレンジの花ですが、この花から紅の染料を作り染物や口紅になりました。染料にするには咲き始めがよいので、外側からこまめに摘んでいきます。そこから「末摘花(すえつむはな)」とも呼ばれています。源氏物語にも登場します。
末候は麦秋至(むぎのときいたる)で、麦の穂が実りのときを迎える頃という意味です。小満に見頃を迎える花には、杜若(かきつばた)があります。水辺に群生しますが、「いずれがあやめかかきつばた」というように美人の形用にも使われます、杜若は万葉集にも詠まれていることからも、昔から日本で自生していた花です。スズランも小満に見頃を迎えます。純白で愛らしいスズランは、可憐なイメージがありますが、花や根に毒が含まれているため取扱いに注意が必要です。ラッキョウは、小満の時期に旬を迎える食べ物です。日本では酢漬けにして食べることが一般的ですが、塩漬けのままや醤油漬けにして食べることもあります。若摘みしたものはエシャロットという名前で呼ばれ、食欲増進効果がある野菜です。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |