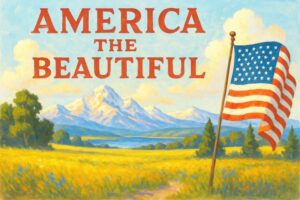大暑

私たちの暮らしのなかには、季節の移り変わりを感じる節目が数多くあります。そのなかでも、夏の盛りを告げる「大暑(たいしょ)」は、まさに一年でもっとも暑い時期の到来を意味する節気です。今年は昨日の7月22日から大暑に入りました。大暑は、二十四節気の第12番目にあたり、「暑気いたりつまりたるゆえんなればなり」といわれるように、気温の上昇が最高潮に達する頃とされます。大暑の頃、日本列島は全国的に梅雨が明け、入道雲が湧き、太陽が照りつける本格的な夏の陽気が到来します。セミの鳴き声が響き渡り、朝から気温が30度を超える猛暑日も珍しくありません。気象庁の観測記録を見ても、1年で最も高温となる記録は、多くがこの大暑から立秋(8月上旬)までの間に集中しています。もっともあまり暑いとセミも鳴かなくなります。このような暑さは、単なる気温の問題にとどまらず、私たちの暮らしや身体にも大きな影響を与えます。農業においては稲の生育にとって重要な時期であり、同時に、熱中症や水分不足に対する注意も必要です。大暑は、自然との関わりのなかで、人がどのように知恵を働かせ、環境に適応してきたかを考えるうえで、非常に意味深い節気なのです。二十四節気には、それぞれをさらに三つに分けた「七十二候(しちじゅうにこう)」という細分化された暦があります。
初候(7月22日頃~):「桐始結花(きりはじめてはなをむすぶ)」
桐の木が花をつける頃。桐は古くから神聖な木とされ、鳳凰が宿る木と伝えられてきました。
次候(7月27日頃~):「土潤溽暑(つちうるおうてむしあつし)」
地面が湿って、蒸し暑さが一層強くなる時期。まさに高温多湿の日本らしい夏の描写です。
末候(8月2日頃~):「大雨時行(たいうときどきふる)」
にわか雨や夕立が多くなる時期。局地的な豪雨に見舞われることもあり、注意が必要です。
これらの七十二候は、古代中国から伝わった気候観察の知見をもとに、日本の風土に合わせて変化してきたものです。現代のように天気予報がなかった時代、人々はこうした自然のサインに敏感に反応し、農作業や日常生活のリズムを整えてきました。大暑には「土用の丑の日」が重なることもあります。これは暦のうえで「土用」に入った後、十二支の「丑」にあたる日を指し、夏バテ予防のために栄養価の高いウナギを食べる風習があります。平賀源内が考案したとされるこの習慣は、現代でも夏の風物詩として定着しています。土用の時期は、土を動かすことが忌まれることから、田畑の作業もひと休みとされ、心身の養生期間でもありました。
大暑の時期には、打ち水や風鈴、うちわなど、日本人が暑さを和らげるために生み出した「涼の文化」が暮らしの中に花開きます。水を打って気化熱で地面を冷やす、風鈴の音で涼を感じるという感性は、日本人ならではの自然との調和の精神を表しています。現代に生きる私たちは、冷房や保冷グッズなど便利な手段に囲まれていますが、自然との関係を見直す機会でしょう。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |