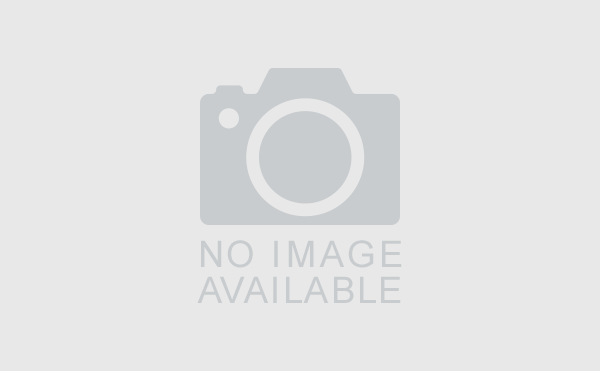日本初のテレビCM放映
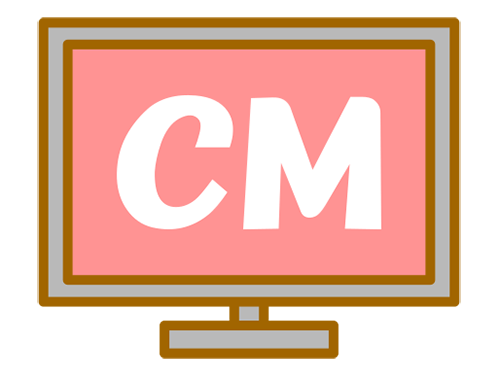
1952年8月29日、日本で初めてのテレビコマーシャル(CM)が放映されました。これは日本テレビが開局する前の公開実験放送で流されたもので、記念すべき「日本初」のCMは、服部時計店(セイコー)によるものでした。時計の秒針が時を刻むシンプルな映像に「精工舎の時計をどうぞ」とナレーションが入る、きわめて簡素なものではありましたが、これが後のテレビ広告文化の幕開けとなります。
1952年は、ちょうどサンフランシスコ講和条約によって日本が主権を回復した年でもあります。戦後の混乱からようやく立ち直り始めた日本では、経済再建と生活向上が国家的課題とされており、その中で「テレビ」という新しいメディアは、単なる娯楽以上の可能性を秘めた技術として注目されていました。当時の日本では、すでにラジオが広く普及しており、家庭で情報や娯楽を楽しむ手段として定着していましたが、「映像が動く」というテレビのインパクトは、当時の人々にとってまさに「夢の装置」と映ったことでしょう。
日本テレビは、正力松太郎(よく「日本のテレビ放送の父」と称されます)が中心となって設立された放送局で、アメリカのNBC(National Broadcasting Company)をモデルに構想されました。民間放送として収益を広告に依存する構造をとったため、テレビCMの導入は日本テレビにとって死活的な意味を持っていました。このため、正式な本放送(9月4日)の前に実験放送としてCMを流すことで、スポンサー企業に「テレビ広告とはどういうものか」を示す必要があったのです。1952年8月29日の服部時計店のCMは、そうした経済的な背景と放送の実務的準備が交差する中で生まれたものでした。現代のCMに比べると、当時のCMは非常に単純で、短く、白黒映像で音声もモノラルです。映像と音声を同期させる技術もまだ不安定で、手作業で編集していた時代です。それでも、企業にとっては、視覚と聴覚の両方に訴えるテレビ広告は大きな魅力でした。「精工舎の時計をどうぞ」という短いフレーズの中には、当時の日本人の生活の中で「正確な時間」が重要視されつつあった社会的背景が見え隠れしています。戦後復興のなかで、人々が勤勉に働き、時間を守り、近代的な生活スタイルを取り入れていく過程と、こうした広告の登場は無関係ではなかったのです。
その後、日本ではテレビが急速に普及し、1953年のNHKテレビ本放送、1955年の民放テレビ各局の相次ぐ開局により、CMの形も多様化していきます。1950年代後半には、有名俳優やアニメーションを使ったCMが登場し、広告そのものが「見る楽しみ」となっていきました。昭和30年代から40年代にかけて、テレビは家庭の中心に置かれる家電となり、CMは視聴者の購買行動を強く左右する存在となります。こうした流れの起点にあったのが、まさに1952年8月29日のこの初CMだったのです。現代ではSNSにもCMが流れ、フジテレビの問題もあって、CMがメディアの命運を変えるようになってきています。テレビの瞬間視聴率という指標もSNSの再生回数と変化してきました。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |