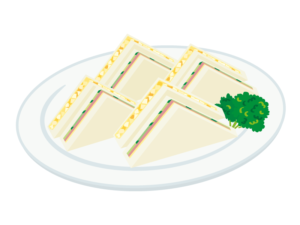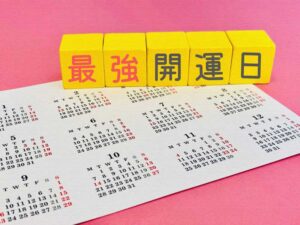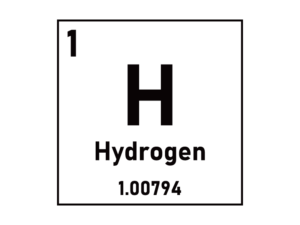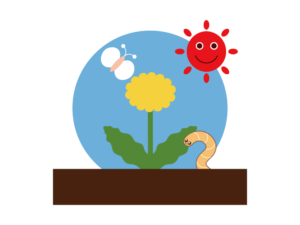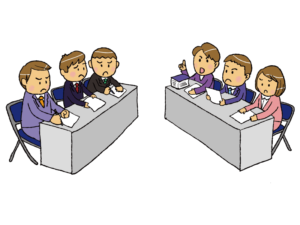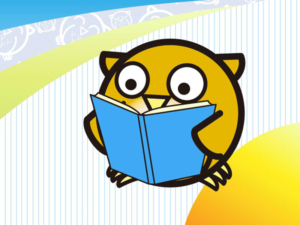その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
聖パトリックの日
3月17日はSt. Patrick's Dayです。日本でも最近は一部でパレードが行われるようになりました。菓子メーカーがあまり騒がないのはなぜなのか、よくわかりませんが、緑にするだけなので、どこかが始めるかもしれません。 聖パトリックはカトリックの聖人で、アイルランドにカトリックを普及させた人です。アイルランド系のアメリカ人が広げた祝日で、今ではイギリスでも広がってきています。ただイギリスもイン・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
財務の日
3月16日は語呂合わせで「ざいむ」の日だそうです。正式な記念日かどうか不明のままですが、通年3月15日が確定申告の期限なので、その翌日ということらしいのですが、もう申請してしまった後にいろいろ考えても遅いですよね。とはいえ、国民はもう少し財務に関心をもってほしい、という気持ちには同感です。「数字は苦手」という人も多いと思いますが、「ふるさと納税」をしてみて、確定申告を自分でするようになってみて、初・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
World Consumer Rights Day
3月15日はWorld Consumer Rights Day(世界消費者権利の日)です。米国第35代ジョン・F・ケネディ大統領が「消費者には権利がある」旨を記載した「消費者の利益の保護に関するアメリカ合衆国連邦議会への特別教書」を1962年3月15日に発表したことに由来して、国際消費者機構が国際デーとして記念日に制定しています。ケネディは消費者の4つの権利「安全を求める権利、知らされる権利、選択・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
如月の満月
本日は旧暦だと如月の十五日、満月です。如月の望月といえば、西行の「願わくは花の下にて春死なんその如月の望月の頃」を思い起こす人も多いと思われます。今年はこの時期に、早い地方なら桜も咲きます。西行がなぜこの日に拘ったかというと、釈迦の入滅の日は2月15日だからです。仏教の僧である西行法師は、出来ることなら同じ日の、桜の花の下で死にたいと願い、実際亡くなったのは2月16日というエピソードが残っています・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
サンドイッチ
3月13日は語呂合わせで「サンドイッチの日」だそうです。313で1が3に挟まれているから、というのと、3が「さん」なのをかけたのだそうです。それなら、303,323でもよさそうな感じもしますが、あまり追及しないことにします。日本ではサンドイッチの略語がサンドになり、いつのまにか、サンドといえば「はさむ」を意味するようになってしまいました。サンドはsandであり、砂のことですから、日本英語で意味が違・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
WWWの日
1989(平成元)年3月12日、イギリスの計算機科学者とティム・バーナーズ・リーとロバート・カイリューが考案したWorldワールド Wideワイド Webウェブ構想を記載した論文を欧州原子核研究機構CERNに Information Management:A Proposalとして提出しました。これが今日、誰もが利用しているインターネットの始まりです。Webは「蜘蛛の巣」のことです。Network・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
3.11
3月11日近くなると、テレビはやたら防災をいい始めます。それは悪いことではないのですが、「災害はいつやってくるかわからない」のですから、本当にその意味をわかっているなら、みんながまだ覚えているこの時期ではなく、まったく関係のない時期にこそ、防災の案内や警告をだすべきでしょう。3月の東日本大震災だけでなく、1月の阪神淡路大震災など、大都市が震災にあったというのは、世界的にも珍しい出来事といえます。大・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
「三つの吉日」が重なる歴史的な開運日
2025年3月10日は、600年に一度とも言われる奇跡的な開運日だそうです。伝統暦法において最高位の吉日とされる「天赦日」、金運の象徴である「一粒万倍日」、そして活力と成長を司る「寅の日」が重なり合います。この三大吉日の同時到来は、古来より「天地の気が最も調和する日」として重視されてきました。 天赦日は暦注の中でも最上級の吉日とされ、すべての障害が取り払われる「万物を赦す日」とされています。この日・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
語呂合わせの多い日2
3月9日も語呂合わせがしやすい日のようです。サン・キューでまず浮かぶのが英語のThnak you.です。そのため何かに感謝する日として制定されていることが多いのです。 「3.9デイ / ありがとうを届ける日」(子どもの健全育成や社会人の人材育成を行っているNPO法人・HAPPY&THANKSが【サン(3)キュー(9)】の語呂合わせにちなんで3月9日に記念日を制定):何に感謝するかが問題ですが、ここ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
語呂合わせの多い日
3月8日はさらに語呂合わせがしやすいせいか、いろいろな記念日になっています。サンとミ、ハチ、ハ、バ、パとの組み合わせは30通りあります。他にも記念日として制定されたものもあるので、数えたことはありませんが、もしかすると一番記念日が多い日かもしれません。 「レモンサワーの日」(レモンの酸(3)とサワーの炭酸がパチパチ(8)弾けるさまの語呂合わせにちなんで):思いつきもしませんでした。「ザンパの日」(・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
十歳(ととせ)の祝い
3月7日は語呂合わせがしやすいせいか、いろいろな記念日になっています。ミナ、サナ、などからいろいろ連想がききます。今回は語呂合わせではなく、3+7=10という計算型の記念日をご紹介します。十歳は二十歳の半分なので、半分成人まで達したというお祝いなのだそうです。「1/2成人式」という言い方もあるそうです。 そうなると、成人が18歳になった現在は、どうするのでしょうね。1+8, 2+7, 3+6, 4・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
元素周期律表
1869年3月6日ロシアの化学者ドミトリ・メンデレーエフがロシア化学会にて元素周期律表を発表しました。誰でも一度は見たことがあると思いますが、その意味をわかっている人は少なく、活用できる人はさらに少ないのが現状です。Wikipediaの解説によると「周期表(しゅうきひょう、英: periodic table)は、物質を構成する基本単位である元素を、周期律を利用して並べた表である。元素を原子番号の順・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
啓蟄の候
3月5日は二十四節気の1つである啓蟄(けいちつ)です。この言葉を聞くと、春が本格的にやってきた、という感じになります。二十四節気は、小寒・大寒・立春・雨水・啓蟄・春分・清明・穀雨・立夏・小満・芒種・夏至・小暑・大暑・立秋・処暑・白露・秋分・寒露・霜降・立冬・小雪・大雪・冬至です。一度に見ることはあまりないかもしれませんが、春夏秋冬以外の言葉も多く含まれていて、自然の移り変わりがわかるようになってい・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
スカーフの起源
3月4日は「スカーフの日」だそうです。語呂合わせがまったく連想できなかったのですが、「日本スカーフ協会が三角形と四角形の「3」と「4」の数字を3月4日に見立てて記念日に制定しております。」(https://netlab.click/todayis/0304#34-3 ダレトク雑学トリビアより)だそうです。なぜ三角形と四角形かというと、「古来ヨーロッパのカトリック圏において、ミサの際に女性が三角形や・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
上巳の節句
今年の3月3日は上巳(じょうし、じょうみ)の節句です。上巳の節句はいわゆる桃の節句、雛祭りです。「上巳」は上旬の巳の日の意味であり、元々は3月上旬の巳の日であったものが、古来中国の三国時代の魏の頃より3月3日に行われるようになったと言われています。今年は巳年でもあり、とくに縁起がいいかもしれませんね。あいにく、日付の方は巳ではなく、未(ひつじ)です。この日は旧暦だと2月4日であり、慶長9年(160・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
アノマリー
パイオニア・アノマリーというのをごぞんじでしょうか。ご存じでしたら、よほどの天文好きです。1972年3月2日に米国のケープカナベラル空軍基地第36発射施設からアトラス・セントールロケットにて打ち上げられたのがパイオニア10号という木星探査機です。1973年12月4日に、木星へ約20万キロメートルまで最接近し、木星やその衛星の画像を送信するとともに、木星の強大な磁気圏やヴァン・アレン帯の観測を行いま・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
日本の労働
3月1日は労働組合法施行記念日です。労働関係の記念日は5月1日のメーデーが知られていますが、これは外国の行事が日本に輸入されたのであって、実質的には1946(昭和21)年3月1日に労働組合法が施行されたことの方が意義深いと思われます。年号からわかるように終戦直後であり、アメリカの影響下であり、この年を境に日本の労働環境が大きく変わったことを示しています。労働組合法は労働三法のひとつで、労働者の団結・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
言語技能測定技術と言語教育㉔ 文法学習は必要か
タイトルの疑問文に対する回答は「学習者には必要ない」です。文法というのは、言語のしくみであり、法則性です。文法を知らなくても運用できることは、母語話者が証明しています。日本人で日本語文法を熟知している人が何人いるでしょうか。アメリカ人で英文法をしっかり学習している人は稀有です。日本人留学生が「文法の神様」になるのは、日本の英文法教育がいかに徹底しているか、という証拠です。英語の得意な日本人で英文法・・・
言語技能測定技術と言語教育㉓ 文法学習
移行法の根幹は母語の知識を活かす、ということなので、どうしても翻訳中心になります。翻訳は、学校でやってきた英文解釈と基本は同じです。学校の英文解釈との違いは、英文解釈の回答は直訳的で、日本語としておかしくても、内容が正しければOKです。翻訳の場合は、著者の意図が正確に伝わることが重視されるため、「意訳」によって、日本語として読みやすいことが求められます。学校の英文解釈では、辞書と文法書が必須です。・・・
言語技能測定技術と言語教育㉒ 移行法
自然法は環境に依存する学習法で、直接法は特殊な出会いにおける本能的なコミュニケーション方法といえます。それらに対し、語学として勉強する場合、母語の知識を活用して、外国語を学ぶという方法がよく使われます。移行法と改めて言われると違和感があると思いますが、学校で習う英語の時間の方法です。辞書を使った英文解釈や英作文、文法学習は日本語の知識が不可欠です。言語習得には、幼児のように、環境から自然に学習する・・・