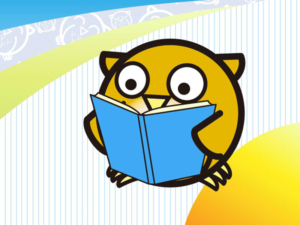その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
言語技能測定技術と言語教育㉑ 直接法
自然法の学習過程をよく観察すると、「その場で、そのものの名前を知る」という方法が多いことがわかります。これを直接法Direct Methodといいます。直接法は語学だけでなく、芸術やものづくりの世界でも「実際に見て覚える」ことがあり、幅広く応用されている学習法です。アフリカで先住民に出会ったヨーロッパ人、オーストラリアでアボリジニに出会ったイギリス人、南米大陸で先住民に出会ったスペイン人、北米で先・・・
言語技能測定技術と言語教育⑳ 学習・訓練法
語学にはいろいろな技法がありますが、需要も多いため、英語教育が最も進化しています。英語教育は、音声言語訓練ですし、文字による学習が主体ですから、手話にそのまま応用できるわけではありませんが、考え方は参考になると思われます。まず英語教育の思想と方法論は、自然法、直接法、伝統法に分けられると思います。手話教育の界隈でよく話題になるのが、ナチュラルアプローチNatural Approachですが、かなり・・・
天皇誕生日
天皇陛下、お誕生日おめでとうございます。こうして国民が陛下のお誕生日をお祝いする、というのはなぜなのでしょうか。誕生日のお祝いというのは家族とか、親しい人、大切な人に対してです。つまり天皇陛下というのは国民にとって、大切な人と考えている、ということになります。この機会に、なぜ天皇というご存在が大切なのかを考えてみるのもよい機会です。世界には王国がいくつもありますが、どの王朝も交代があり、日本の皇室・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑲ 表現試験2
1級は手話技能検定試験の最上級ですから、課題文、自由文ともかなりのレベルが要求されます。試験制度設立当初は、対話能力を重視していましたから、「手話による討論」という試験方法を採用していました。しかし、あまりに受験者が少なく、合格者も少なかったため、試験方法を変更しました。また、討論形式は苦手な日本人が多いのと、遠慮がちな人や、反論を述べることに抵抗感のある人も多い、という日本文化もあり、成功しませ・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑱ 表現試験1
手話技能検定試験では、3級までは、「ビデオを見て、選択肢で回答を選ぶ」という「理解度」の試験です。これは、前述の理解語彙と使用語彙の原理に依っています。学習初期段階では、理解語彙と使用語彙の範囲はほぼ同じなのですが、学習が進むにつれ、使用語彙の範囲をはるかに超えた理解語彙をもつようになります。つまり、学習者の理解度を測定するには、理解語彙をテストすればよいのは中級程度まで、ということになります。手・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑰ Useful Signs
手話技能検定協会のホームページに「Useful Signs検定」というコーナーがあります。(https://www.shuwaken.org/UStest/index.html) 解説のPDFには「Useful Signs 検定は、テキストにより自分で学習していただきその結果を測るところが違います。従って合否判定はせず、点数だけをお知らせします。」「受験は有料ですからお金がかかりますが、学習だけな・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑯ 手話数字の歴史的変化
数字については、文化差があります。欧米では千以上を3桁で考えます。日本は4桁です。日本以外では中華系の文化だけのようです。日本の4桁文化は古代中国から来たようなので、同じなのは当然でしょう。この桁という文化は言語と深くつながっているので、まず変わらないと予想されます。現在、数字の桁につけられるカンマ(,)は西洋式になっています。そのため、日本人がアラビア数字を読む時、面倒です。さすがの明治維新も桁・・・
雨水の候
「雨水(うすい)」と聞くと、「春が近くなってきた」と思うのは、昔の人に近づいているから、かもしれません。あるいは女の子がいる家では、そろそろお雛様を出さなきゃ。と思う時期です。雨水とは、雪が雨へと変わって降り注ぎ、降り積もった雪や氷もとけて水になる頃という意味です。二十四節気の1つで、雨水の前が立春、雨水の後は啓蟄(けいちつ)となります。雨水の頃は、実際にはまだ雪深い地域もありますが、厳しい寒さが・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑮ 手話数字
指文字に多くの手話数字が入っている、ということは歴史的には、指文字より先に手話数字があった、という証拠になると思います。たぶん誰もそう思っていないらしく、そういう主張や論文を見たことがありません。しかし、手話研究としては重要な視点だと思います。指文字も大曾根G式になるまでに、いくつもの試作があり、その後も栃木式などの改良がありました。同様に手話数字も現代のようになる前には歴史があります。手話数字の・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑭ 指文字学習
「指文字の読み取りがむずかしい」という話をよく聞きます。これは単純に「学習不足」に起因するのですが、指文字を作ることが比較的易しいことからくる誤解です。日本語だと、五十音の文字を最初に習いますが、文字を学習する時にはすでに音韻は習得済です。頭の中にある音のイメージと文字の形を一致させる学習が文字学習です。指文字の場合は、すでに学習済の文字と指文字の変換という学習過程です。しかも、音と五十音の関係は・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑬ 指文字のしくみ(変化音)
五十音の作成も後半はかなり苦労したようすで、起源も無理が見られます。大曾根以前の指文字では、文字になんとか似せようと、無理な手型を創案していました。そのため実用となると、むずかしく普及しませんでした。いわば机上論であったのに対し、大曾根グループ(以下G)はなんとか実用に近づけたため、今日でも使用されています。大曾根グループ式の特徴の1つが濁音、促音、拗音などが動きで表現されることです。日本語の音韻・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑫ 指文字のしくみ
日本の指文字は聴者が作りました。いろいろな試作がありましたが、現在の指文字は大曾根源助という大阪ろう学校の教員が、仲間と作った、というのが定説になっています。彼は渡米して、かのヘレンケラーに会ったり、ろう学校を見学する中で、聾児に国語を指導するには指文字が必須であると痛感し、アメリカ指文字を参考に日本指文字を考案したとされています。指文字を見るとわかるように、アメリカ指文字を起源とするものが多いの・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑪ 指文字による借入
日本の指文字は世界と比べると、かなり特殊なしくみになっています。日本語はすべて仮名で書こうと思えば可能です。書き言葉は「漢字かな混じり文」なので、実際には仮名だけだと、同音異義語や「送り仮名」の規則などがあって、かなり複雑な仕組みです。そのため、国語学習に多くの時間を費やしています。江戸時代までは、国民の多くが「文字が読めない」人が多い、つまり識字率が低かったのですが、それでも平仮名はなんとか読め・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑩ 指文字とは何か
「指文字は簡単」という「神話」ないし「都市伝説」があります。これは日本の指文字がモーラという音節に対応していて、ひらかな、やカタカナという文字もモーラに対応していることに関係があります。指文字は「文字を手で表現する方法」なので、欧米などでは、アルファベットに対応し、日本では仮名に対応するシステムです。アルファベットの場合、文字が26しかなくて覚えやすい代わり、組み合わせである綴りがあって、けっこう・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑨ 会場試験とWEB試験
手話技能検定試験では、数年前からWEB試験を開始しました。これは新型コロナによる会場試験ができなかったことと、台風などにより中止になる会場が出てきたためによる対策です。また会場試験は当初、できるだけ多くの会場を設置することを目指していましたが、会場の借り出しには厳しい条件がありました。多人数にビデオ画像を提示する必要があるのですが、そうした施設をもっているのは、大学などの学校に限られます。そして、・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑧ 転記時間
手話技能検定試験では、独自の試験方法を採っていることがいくつかあります。その1つが転記時間です。6級から3級までの試験では「ビデオを見る」「選択肢をマークカードに記す」という回答手段を採っています。マークカードにマークする、という作業は、小さい楕円形のマルを鉛筆で塗りつぶすという作業なので、けっこう集中力がいる上に、時間がかかります。試験問題はビデオで示されるので、そちらにも集中しないといけません・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑦ 手話の語彙数と文型数
よくある質問に「手話の単語はいくつくらいあるのですか?」というのがあります。この質問の前提として「手話の単語は少ない」という誤解があります。そもそも言語の単語数つまり語彙というのは「無限」です。単語は次々に生まれていくと同時に死語になって廃れていく語もあります。語は「語形成」というしくみがあって、組み合わせによって、いくらでも作れるようになっています。しかし、「辞書に載っている語」が語彙という誤解・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑥ 試験範囲語彙の階層化
手話技能検定協会のホームページをみていただくと「初めての方へ」というページに「手話技能検定の級とレベル」が示されています。(https://www.shuwaken.org/first/first.html)そこに「単語数・例文数」が示されています。6級は「単語数:100程度:動きのある指文字(濁音・半濁音など)・数字」となっています。もっとも基本的と思われる手話語彙を100語、選んでいますが、前・・・
言語技能測定技術と言語教育理論⑤ 使用語彙測定技術
手話技能検定試験のレベルの設定において、「理解語彙と使用語彙」という概念を用いています。下級レベルは理解語彙と簡単な文法が含まれる文型の試験です。理解語彙は上級者になると、個人差や学習経験による差が大きくなり、試験範囲の公開も困難になってきます。そこで、上級者には使用語彙の測定と文法習得を測定する必要があります。これは手話をビデオで提示して、選択肢で回答を得る、という方法では不可能です。受験者に手・・・
言語技能測定技術と言語教育理論④ 理解語彙と使用語彙
手話技能検定試験のレベルの設定において、「理解語彙と使用語彙」という概念を用いています。たとえば、大阪地方に住んでいる人は普段、「大阪弁」を「使用」します。東京地方に住んでいる人は普段、「大阪弁」は「使用」しませんが、「大阪弁」はほぼわかります。この例でわかるように、人は自分の使う語の何倍もの語が理解できます。そこで自分の使う語群を「使用語彙」、理解できる語群を「理解語彙」と呼びます。母語話者は使・・・