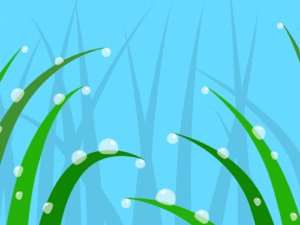手話の雑学6

アメリカは多様化こそが文化であり、それが政治的分断の原因の1つであることも知られています。他にも、中国の政府は必至に統一を図ろうとしていますが、現実には民族が多様化し、それに伴い言語も多様化しています。言語は「普通話」という北京語を全国に浸透させようとしていますが、実際にはまだ方言が色濃く残っています。宗教は建前上禁止という形で統一を図ってはいても、実際には多様な宗教が残ったままです。料理は日本でも知られているように、北京料理以外の広東料理、四川料理などが日本でも人気です。そして最近では「日式」という日本風の「中華料理」が人気でもあります。裕福な人々の間で人気なのが、日本料理です。政治的に「反日」を訴える人も日本製のカメラを使い、マンガを読み、日本食を食べているわけです。つまり文化的な規制は「文化大革命」の例を見るまでもなく、言語統制と同様に不可能と考えるべきものです。世界の大きな国家を見ただけでもこういう状態であり、インド圏や中東やアフリカなど、日本には馴染みの薄い地域でも同じような多様性が普通の状況です。そして、その違いを巡る争いは絶えません。
こうした世界の社会状況を見据えた上で、手話とその主たる話者とされる聾者をどうとらえたらよいか、という問題がずっと続いています。「ろう文化」とよく言われますが、聞こえないことから起こる行動については、人類共通の部分が想像できますが、世界中がすべて同じかというとそうでもありません。聾者同士のコミュニケーションを見ると、共通部分もあれば、違う部分もあります。聴覚障碍者にとって、重要な補助器具である補聴器に対する考え方もさまざまです。さらに補聴器から進化した人工内耳についても、考え方や受け入れ方に違いがあります。また、あまり知られていませんが、宗教の違いによる聾団体組織の違いもあります。それは宗教によって、聾であることへの思想の違いがあるからです。聾文化も多様的なのです。
手話がその国の音声言語と文化の影響を強く受けていることはよく知られています。実際、日本の手話とアメリカの手話と中国の手話はかなり違いが見られます。しかし、日本語と英語と中国語の違いほど、大きくは違わず、似ている部分、共通の部分がたくさんあります。世界の手話の共通部分は、身振りの共通部分とかなり一致するのですが、そうでない部分もあります。その区分けは微妙で、線引きが非常にむずかしいのです。それでも手話の語つまり語彙が非常に似ている手話があります。現在の欧米の手話は、日本や中国の手話と比べると、互いによく似ています。正確な数字ではありませんが、イメージとしてとらえていただくと、たとえば日本の手話とアメリカの手話の語彙の相似度は20%くらいです。それでも音声言語と比べると、音声言語ならば相互に親縁関係があると判断される程度に似ています。しかし実際には、日本の手話とアメリカの手話の親縁関係はありません。それは歴史的に証明できます。欧米の手話の相互類似度は80%以上あります。そしてそれには聾教育の歴史が関係しています。詳しい説明は手話関係書籍をぜひ読んでください。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |