白露(はくろ)
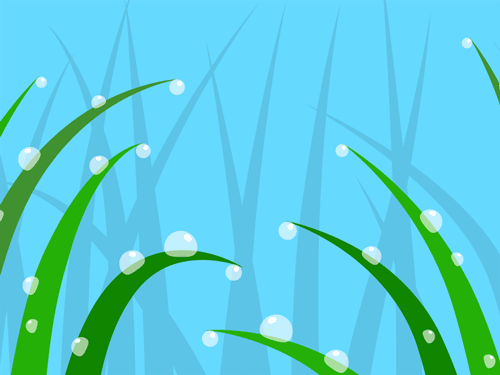
二十四節気の一つである「白露(はくろ)」は、今年は9月7日です。朝夕の空気がぐっと冷え込み、草花の上に白い露が宿るようになるとされていますが、今年は猛暑の影響で事情が違うようです。暦の上では秋の深まりを告げる節気であり、夏から秋への季節の移ろいを感じさせる大切な節目です。 二十四節気は農耕や生活の目安として長く受け継がれてきました。その一つひとつをさらに細かく分けたのが「七十二候(しちじゅうにこう)」です。五日ごとに季節の変化を表し、自然の細やかな移ろいを表現しています。白露には三つの候が配されており、自然界の変化を豊かに映し出しています。
初候「草露白(くさのつゆしろし)」
草の葉に白い露が結び始める時期を意味します。夏の名残がまだ残る日中とは対照的に、朝夕の冷え込みによって空気中の水蒸気が露となって草木を濡らします。朝日を受けて光るその景色は、秋の始まりを実感させる情景です。日本の文学では露は「儚さ」の象徴として多く詠まれ、和歌や俳句に登場してきました。
次候「鶺鴒鳴(せきれいなく)」
鶺鴒(せきれい)が鳴き始める頃とされます。鶺鴒は長い尾を上下に振る特徴的な小鳥で、日本の民間伝承や神話にも登場します。『古事記』には、男女の契りを教えた鳥として描かれており、古代の人々にとって特別な存在でした。白露の季節にその鳴き声を耳にすると、秋の情緒が一層深まるのを感じられます。近頃はあまり見かけないようです。
末候「玄鳥去(げんちょうさる)」
ツバメが南方へ渡っていく時期を指します。春に日本へ飛来し、人々の暮らしの中で巣を作ってきたツバメは、この頃になると子育ても終え、暖かい地を目指して旅立ちます。ツバメの去りゆく姿は、夏の終わりと秋の到来を実感させる情景であり、人々に一抹の寂しさを与えます。
白露の頃は、昼間はまだ残暑が感じられるものの、朝夕は肌寒さを覚えるようになります。稲穂は実を重くし、収穫の時期が近づきます。農家にとっては台風や長雨に注意を払いながら、実りを確実に迎えるための大切な時期です。また、梨や葡萄など秋の果物も旬を迎え、食卓が豊かになる頃でもあります。また、白露は中秋の名月に近い時期でもあり、月を愛でる「お月見」の風習とも深く結びついています。澄んだ空気に浮かぶ月と、草葉に光る露の取り合わせは、日本人の美意識を映し出す象徴的な光景といえるでしょう。古来より露は、儚さや無常観を象徴するものとして文学や芸術に取り入れられてきました。同時に、朝日に輝く露は短くとも鮮烈な生命の輝きを表すものでもありました。こうした二面性が、白露の持つ魅力をより深めています。白露と七十二候は自然の微細な変化をとらえ、人の心に季節を映し出す文化的な財産です。露に光る一滴の水の中に、私たちは生命の儚さと美しさを見いだしてきました。白露の時期を迎えるとき、自然に耳を澄まし、季節の息遣いを感じるひとときを大切にしてみてはいかがでしょうか。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |

