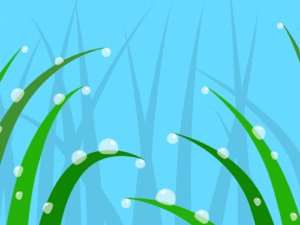手話の雑学7

ヨーロッパの手話の始まりはフランスの聾教育からであることが知られています。18世紀半ば、ド・レペという神父が手話による聾教育を始めたとされています。ド・レペ神父は聾児たちにフランス語を教えようとして、その手段として手話を用いたわけです。日本では少し誤解が広がっていますが、ド・レペ神父はフランス語を教えるために手話を用いたわけです。日本でいう「日本語対応手話」という表現を借用すれば、「フランス語対応手話」です。そもそも手話には文字がないので、文字による教育をするには、その国の音声言語の文語を学習するしかありません。そのための手段として手話を用いたわけです。一方で、音声言語を音声から教えようとするのが口話法という聾教育法です。客観的に見れば、聾教育の目的はその国の公用語である音声言語を教えることであり、その手段として手話を用いるか、音声を用いるかの違いということです。言語として手話を教えるという思想は現代アメリカで発展してきた思想であり、そのアメリカでも手話に文字がないことに対する解決はなされておらず、結局、英語をいかに習得させるか、という教育目的は今も変わりません。
それはともかく、ド・レペ神父が用いたその手話がヨーロッパ各国やアメリカに伝わり、それぞれ少しずつ変化しながら現在に至っています。アメリカ手話はさらにアフリカなどにも伝わり、世界の多くの国で手話が欧米系の手話になっているのが現状です。ある意味、英語が世界の共通語になっているのと似たような状況であり、欧米系手話が国際手話の元になっています。日本は19世紀半ばに聾教育が開始されましたが、手話は文明開化の波に乗らず、日本独自の進化を遂げていきました。現在、日本と韓国と台湾の手話が相互に似ていることが知られています。その歴史的背景は20世紀の日本の支配と関りがあります。日本はそれまで聾教育のなかった朝鮮半島と台湾に聾教育を推進し、そこで日本の手話を用いました。それはアメリカ手話がアフリカで聾教育を推進すると同時にアメリカ手話を広めていったことと相似関係にあります。太平洋戦争後、朝鮮半島と台湾はそれぞれ日本から分離され、手話も現地語の影響を受けつつ独自に進化していきましたが、今も共通性を多く残しています。
欧米系の手話の親縁性が聾教育の歴史と結びついているように、日本系手話の親縁性も聾教育と結びついています。言い換えると、手話と聾教育は一体であり、音声言語の分布とは別の分布になっています。つまり民族や人種、宗教とは結びつかない形の相互親縁性があります。しかしそれは世界共通ではなく、音声言語の語族に似たような群れを作っています。昔の考え方では、言語と文化、民族、人種、宗教という要因の一致で分類していたのが、そこにさらに教育を加えるかどうか、というのは議論の余地があります。世界の聾世界では、聾であることを要因としてまとまる、という思想もあります。言語と文化を共有しているので、「ろうも民族」という思想もあり、そういう運動もあります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |