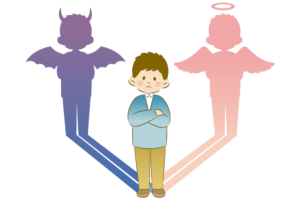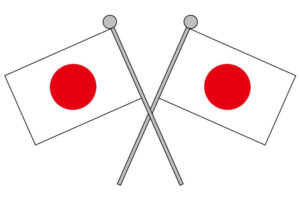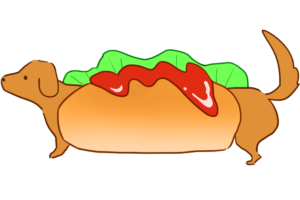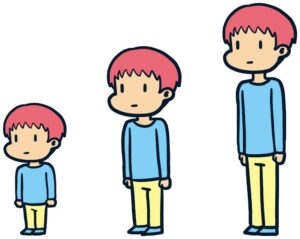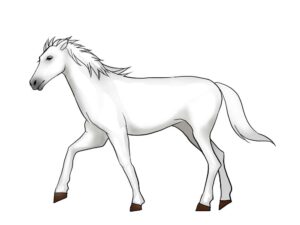その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
閏日
2月29日は「肉の日」です。今年は「肉の日」が1日多いので、肉屋と焼肉屋が「潤う日」だから「うるう」ではありません。第一、「閏」と「潤う」では漢字が違います。閏は「門の中に王がいる」という意味で、昔の中国では閏日は普段、外にでる王が、この日は門の中に閉じこもって政務をとらない、つまり仕事をしない、という由来があるそうです。潤の方は今では水分ばかりを連想しますが、「財布の中が潤う」のように財貨が増え・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
倫理の衰退
最近のマスコミなどの記事ではパワハラ、セクハラなどに加えて政治家の裏金問題や芸能人のスキャンダルが非常に目立ちます。これらに共通するのが「倫理観の欠如」ということです。現在では倫理といっても、具体的にどういうことなのか、答えられる人は少ないのではないでしょうか。倫理の定義はシンプルなもので「人として守るべき正しい道」ということです。いわば善悪の判断の根拠ということですが、人によりその基準が異なるの・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
春の支度
小正月と雨水が過ぎ、しばらくは行事がありません。春の訪れが実感できる昨今は、春から始まる作業への準備期間です。今は新暦で行事が進行していきますが、それでも4月からは進学や就職、新事業などが始まることも多いと思います。最近はいきなりスタートというか、昔はプレーボールという表現だったのが、キックオフという、野球からサッカーに用語が変わったあたりから、いきなり始めるのが普通になってきました。しかし何事に・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
初庚申
今年の新暦2月26日、旧暦1月17日は干支の庚申になり、今年初の庚申となります。ちなみに今年の庚申は2月26日、4月26日、6月25日、8月24日、10月23日、12月22日です。干支は60日で1周しますから、60日毎にあります。新暦は月の日数が不規則なのでわかりにくいですが、旧暦は30日毎なので、すぐにわかります。 庚申の習慣が日本に伝わったのは平安時代だそうですが、庶民に広がったのは江戸時代で・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
閻魔賽日と藪入り
旧暦睦月と文月十六日は閻魔賽(さい)日です。この日は藪入りでもあります。閻魔は死後の世界において人々の善悪を裁くとされる閻魔大王です。この日は地獄の釜の蓋が開き、亡者たちが一時的に苦しみから解放されるとされています。地獄も藪入りなのです。この日に閻魔大王を祀る寺院へお参りし、罪や過ちを犯した人々が、自らの行いを懺悔し、閻魔大王に赦しを乞うために訪れるのです。普段の生活で罪や過ちを犯したことのない人・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
睦月満月の小正月
2月24日は旧暦睦月十五日、初満月です。そして小正月です。昔は初の満月の日に小正月祝いをしていたのです。無病息災や家内安全などの祈願をします。小正月は別名を女正月(おんなしょうがつ・めしょうがつ)ともいいます。昔は元旦を男の正月としていたので、小正月を女の正月と呼ぶようになりました。女正月は年末年始にゆっくりと休めなかった女性たちが、ゆっくりと休養したり遊んだりする日でもあります。今では新暦の正月・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
天皇誕生日
2月23日は天皇陛下のお誕生日です。今年は金曜日なので3連休の人も多いと思います。今上陛下のお誕生は既に新暦の時代ですから、新暦でお祝いするのは当然です。ただ旧暦だと、この日は丁巳(ひのとみ)で、陰陽五行では、十干の丁は陰の火、十二支の巳は陰の火で、比和だそうです。比和(ひわ)の意味は「同じ気が重なると、その気は盛んになる。その結果が良い場合にはますます良く、悪い場合にはますます悪くなる」とのこと・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
内包的意味と借用語
内包的意味に文化差が反映される例を説明しましたが、外来語を借用するとその差はさらにひろがります。日本語には英語からの借用語が多く、近年とくに原語とはかけ離れた意味になっているケースが増えてきました。これは辞書の外延的意味だけしか知らないか、意図的に意味をねじまげて借用しているからです。 たとえばマンションは日本では高層の集合住宅を意味しますが、英語のmansionは「屋敷」という意味であり、広い庭・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
内包的意味の文化差
内包的意味は個人差あるいは集団差という説明をしましたが、この集団には地域や国家、民族などいろいろな形があります。とくに問題になるのが言語間のニュアンスの違いです。たとえば犬は英語でdogといいますが、外延的意味はほぼ同じですが、内包的意味に大きな差があります。英語のa hot dogは犬の意味はまったくなく、日本語でもホットドッグのようにいうことで、違いを示しています。英語でなぜa hot dog・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
内包的意味connotation
Connotationは含蓄と訳されることもありますが、dennotation外延的意味とセットで考えないと誤解が生じます。外延と内包という用語は難しいニュアンスがありますが、簡単にいえば、外延的意味というのは誰もが同じ内容を思い浮かべることができる意味であり、内包的意味というのはいわゆるニュアンスのことで、人により感じる意味が異なる印象のようなものです。この2つの意味の境界が曖昧で、外延的意味は・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
雨水(うすい)と雛飾り
2月18日は二十四節気の雨水です。二十四節気は太陽の運行なので、新暦でも時期はほとんど変わりません。雨水は「うすい」と読みます。アマミズではないので誤解のないように。今では二十四節気よりも「雨水タンク」のような用例の方が多いですね。雨水とは、雪が雨へと変わって降り注ぎ、降り積もった雪や氷もとけて水になる頃という意味です。実際にはまだ雪深い地域もありますが、厳しい寒さが和らぎ暖かな雨が降ることで、雪・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
大坂城炎上と歴史
旧暦慶応4年1月18日(1868年2月2日) 大坂城は炎上しました。戊辰戦争の時、旧幕府軍から新政府軍への大坂城の引き渡しの最中に出火したとされています。今では新暦の方が採用されて解説も2月2日としていることがほとんどですが、本当は旧暦で表示するべきでしょう。1583年(天正11年)から1598年(慶長3年)にかけて豊臣秀吉が築いた大坂城(豊臣大坂城)の遺構は、現在ほとんど埋没しています。現在地表・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
色名の文化
白馬と書いて「あおうま」と読ませるのは、知識がないと絶対に読めないものです。こういう特殊な読み方だけでなく、「当て字」といわれる特殊な読み方があるのも日本独特の習慣です。外国語でも、特殊な読み方がないわけではないのですが、例外的です。劇作家バーナード・ショウが作ったとされるghotiはlaughのgh、womenのo、nationのtiなのでfishと読むのだというのはジョークです。 日本語のアオ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
白馬節会と人日の節句、七草粥
旧暦1月7日に「白馬節会(あおうませちえ)」が宮中では行われていました。白馬と書いてアオウマと読むのは由来があります。白馬節会が始まった当初は中国の故事に従い、ほかの馬よりも青み(鴨の羽の色)をおびた黒馬(「アオ」と呼ばれる)が行事で使用されていました。醍醐天皇の頃になると白馬または葦毛の馬が行事に使用されるようになりましたが、読み方のみそのまま受け継がれたため「白馬(あおうま)」となったとされて・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
六日年越し
旧暦1月6日には旧暦1月7日の「七日正月」の前日として、「年越し」の行事が行われていました。七日正月というのもおもしろい習慣で、本来は「人日(じんじつ)の節句」です。人日の節句とは、日本における五節句の一つであり、その中でも特に新年を祝う節句です。人日の節句は、1月6日の「六日年越し」と1月7日の「爪切りの日」という日本の伝統的な行事とも関連があります。六日年越しは、新年の悪霊を追い払い、無病息災・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
初水天宮
旧暦1月5日に水天宮にお参りすることを初水天宮といい、初詣とは別の意味があります。初水天宮とは1月5日に東京か福岡県のどちらかの水天宮に参拝することです。水天宮は水と子供を守護し、水難除け、漁業、海運、農業、水商売、また安産、子授け、子育ての神様となっています。東京の水天宮の歴史は江戸時代までさかのぼります。福岡県久留米市の水天宮を信仰していた久留米藩主第9代の有馬頼徳(ありまよりのり)が、参勤交・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
旧暦睦の御用始め
旧暦では1月4日に「御用始め」をするところが多かったようです。もう新暦では2月中旬ですから、今更の感じがすると思います。「西洋式の商慣習が普及する以前は、1月2日に普段の仕事を形だけ行い、その年の労働の安全や技能の上達を願うならわしがあった。」そうです。(https://ja.wikipedia.org/wiki/仕事始め) 「農村では田畑に鍬を入れたり、縄作りの作業を始め、田の神を祀って米や餅な・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
旧暦睦月三日
この日はめでたい正月の内のせいか、天皇の即位がいくつか行われています。仁徳天皇1年(313年) 第16代天皇仁徳天皇が即位されました。仁徳天皇は大阪府堺市にある天皇陵で有名です。即位元年に難波高津宮に都を移しました。即位4年、人家の竈(かまど)から炊煙が立ち上っていないことに気づいて3年間租税を免除したという逸話も有名です。そしてその間は倹約のために宮殿の屋根の茅さえ葺き替えなかったという逸話が記・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
大の月と小の月
新暦の不合理についての続きです。新暦には大の月と小の月があります。月によって31日の月と30日の月がありますが、不規則のため、いろいろな覚え方がありますが、日本では「西向く侍」として2,4,6,9,11月が大の月であると覚えます。日本的な語呂合わせを利用しています。英語圏では歌で覚えるそうです。Thirty days hath September,(三十日は九月、)April, June, and・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
旧暦正月
明けましておめでとうございます。本日は旧暦令和五年元旦です。先日、立春で新年が始まったという「古い」感覚の方もおられると思いますが、暦の上では本日から新年が始まります。従って今日から旧正月となります。伝統的なお正月の行事をしてみるのも新たな感覚になってよいと思います。肝心の神社やお寺はもう新暦で動いていますが、初詣もゆっくりできます。 今年は新暦だと閏年で、2月29日があり、しかも休日が2日もあっ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles