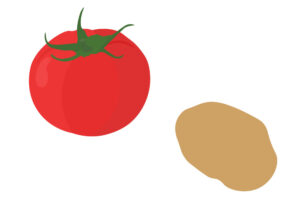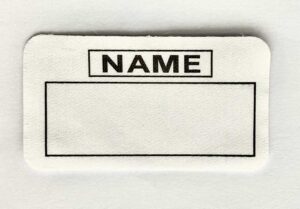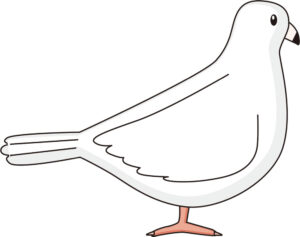その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
欧米の古戦場
日本の古戦場はほとんどが住宅に埋め尽くされ、昔の面影はわずかに残る土塁とか小山と碑だけということが多いのですが、欧米の古戦場は当時の面影を残していることが多いというのが個人的な印象です。理由は簡単で、城の大きさと建築方法にあると思われます。日本の城は天守閣を中心にして、堀や土塁で周囲を囲む形が一般的で、現在、堀は埋められて道路になっていたり、土塁は崩されて、一部に石垣が残っているだけです。天守閣も・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
小牧・長久手の古戦場
「どうする家康」は小牧・長久手の戦いに入ります。天下分け目の戦いといえば関ヶ原の戦いをイメージする人が多いのですが、個人的にはこの戦いが家康と秀吉の実質的な戦いであり、分け目だと思っています。結果的に勝敗が曖昧でしたが、それは家康の戦略であり、最終戦は大阪冬の陣と夏の陣で豊臣家を滅亡させるので、これが最終戦です。しかしその前の関ヶ原の戦いで趨勢は決まっていました。すなわち家康対秀吉の争いは、小牧・・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ことばの意味と存在
ことばにはいろいろな意味がありますが、その1つに言霊(ことだま)というのがあります。ことばには魂が宿り、それが現実の世界に反映するという思想です。物理学ではありえないので、迷信として排斥する人もいますが、一方で、相手を呪ったり、神様や仏様にお願いする時にもことばでするので、言霊をまったく信じないなら無意味な行動ということになります。ことばを物理的に解析することは非常に難しいです。音声を物理的に研究・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
間違った命名
人が物に名前をつける時、植物や動物の和名はなんとなくイメージができたりするのは、何かに例えていることが多いです。中にはニセ○○とか○○モドキとか可哀そうな名前のこともあります。またイヌ○○のように犬が可哀そうな場合もあります。 たとえができない場合、つまり初めてみるような物の場合は困ります。外国探検中の時は現地人に物を指差して??のような表情でたずねることになります。この時、こちらが指している物と・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
名前の重要性
人間は名前がないと物の認識ができない、とされています。草花も名前を知らないうちは雑草ですが、名前を知ると識別ができるようになり、愛でる気持ちになります。動物にも個体別に名前をつけることで親近感がわきますから、ペットには個別の名前をつけます。空の星も星座名を知らなければ、光の点でしかありません。 名前は人が付けます。そこに名づける人の意図が反映されます。専門用語も名前の一種ですが、専門家だけがわかる・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
送り火
8月16日は送り火の日です。13日にお迎えしたご先祖が帰られるのを惜しんで火を焚いてお送りするものです。有名なのは京都の大文字焼ですね。火を焚いてお迎えし、火を焚いてお送りするという風習は火が神聖なもの、という思想で、世界共通のようです。電気がなかった時代は明かりといえば蝋燭や篝火(かがりび)、松明(たいまつ)でした。今でも蠟燭や灯明(とうみょう)を灯します。一方で火事の危険もあるので、火の用心に・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
終戦記念日
8月15日は終戦記念日です。日本ではこの日に玉音放送があり、天皇から国民に敗戦を伝えたことをもって終戦としています。どの時点をもって敗戦とするか、についてはつねに議論になります。日本の敗戦は連合軍のポツダム宣言を受諾したことをもって敗戦とするというのが国際的な認識なので、論理的には9月2日に降伏文書に署名しているので、その日を終戦とするのが正しいのかもしれません。しかし8日15日の玉音放送をもって・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
専売特許
8月14日は専売特許の日です。「1885年(明治18年)のこの日、日本初の専売特許が交付された。7月に施行された「専売特許条例」に基くもので、特許第1号となる堀田瑞松の「錆止め塗料及び塗り法」ほか7件が認められた。彫刻家で漆工芸家であった堀田氏は、鉄船用の塗料として漆などを原料に開発し、その改良品は日本海軍だけでなくロシア海軍の軍艦や米ガス会社のタンクにも使用され、日本初の世界的な発明となった。」・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
迎え火
8月13日は新暦でお盆をする人にとって、ご先祖様をお迎えする迎え火を焚く日です。火を焚いて迎えるという習慣は日本独自のものではなく、近年、日本だけでなくアジアに広がっているハロウインでも、根本であるドルイド教では、火を焚いて霊を迎え、新年を迎える習慣がありました。それがハロウインのカボチャの灯火へと変わっていきました。蠟燭の灯火は焚火の変形とも考えられ、火を焚くことが悪霊を追い払うという思想は世界・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
君が代
8月13日は国家君が代の日です。1893年(明治26年)のこの日、文部省が訓令「小学校儀式唱歌用歌詞並楽譜」を布告し、小学校の祝日・大祭日の唱歌に『君が代』『一月一日』『紀元節』など8曲が定められました。『君が代』の歌詞は、『古今集』の読み人知らずの和歌に、イギリスの軍楽隊長フェントンが曲を作り、歌われていました。しかし、メロディーと歌詞が一致していないということなどで、それを宮内庁雅楽課の林広守・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
山の日
8月11日は山の日という祝日です。「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」ことを趣旨としている、そうですが、抽象的でよく意義がわかりません。Wikipediaによると、制定の経緯は 「国民の祝日として「山の日」を制定することを求める日本山岳会をはじめとする全国「山の日」協議会加盟諸団体や既に「山の日」を制定していた地方自治体、その他山岳関係者や自然保護団体等からの意見を受け、2013年4月、超・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハトの日
8月10日は語呂合わせがしやすいので、たくさんの記念日があります。ハト、ハート、ハット、ハントなどの同音語だけでなく、ハにはバやパにもなりますし、8もハチやヤにもなります。10はトウだけでなく、ジュウ、テンなどにも替えられます。これらの組み合わせとなると、想像ができない数になりそうです。日本語の同音異義語や語呂合わせという言葉遊びの本領発揮という感じです。https://zatsuneta.com・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
Indigenous People
8月9日はInternational Day of the World's Indigenous Peoplesです。1994年12月の国連総会で制定された国際デーの一つです。日本ではこれを国際先住民の日と訳しています。世界には推定3億7000万人の先住民がおり、90ヵ国に住んでいます。先住民は人権・環境・開発・教育・健康・経済・社会開発などの分野において問題に直面しています。国際社会は、先住民の・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
立秋
まだまだ暑いですが、今年は8月8日が立秋です。旧暦では6月22日ですから、なんとも不思議な感覚です。二十四節気は太陽の運行ですから、新暦とは近いのですが、それでもまだ早い気がする一方で、旧暦だと1か月以上の差があって、今年のように閏月があるとなおさら差が大きくなります。昔の人はどう思っていたのでしょうか。そもそも暦の日付はあまり気にしていなかったのかもしれません。暦は行事のためにだけあり、実際の季・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
はてな
8月7日は語呂合わせだとハナです。そこで「はてな」について一席。有名な落語に「はてなの茶碗」というのがあります。上方落語で、関東では「茶金」というそうですが、個人的には上方の方をよく聞きました。あまり詳しく書くとネタバレになりますが、茶金のいうのは茶屋の金兵衛の省略です。茶屋といっても大きな今でいう骨董屋さんで、お公家さんの家にも出入りしている大商人です。この茶金さんが清水寺の茶店でお茶を飲みなが・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハローは日本英語
誰でも知っている「ハロー」は英語で書くとhelloです。そのまま読めばヘローですね。実際に英会話とか映画が聴くと、ハロウとロウの方にアクセントがあり、日本語ではハの方にアクセントがあるので、微妙に違っています。英会話の時は、状況からして聞き間違うこともないし、相手も気にしていませんから、そのまま通用してしまいます。これは外国人が「コニチワ」と発音していても、「ああ外国人だな」と思うだけで気にしない・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハンコの日
8月5日は「ハンコの日」です。このハンコという日本独特の制度は最近、公文書や私文書でも省略する方向に進んでいます。確かに押印するのは面倒な作業ですが、代わりに自著するのはもっと面倒です。ハンコの起源は中国ですが、現在の中国には印鑑制度はないそうです。 ハンコは「読んだ」あるいは「承認した」という意味を示しています。日本以外では署名(サイン)がその機能を果たしています。ハンコには三文判といわれる既製・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハシの日
8月4日は「ハシの日」と聞いて、何の日を連想されるでしょうか。橋、箸、端?さらに捻れば嘴や土師なども辞書からでてきます。記念日に語呂合わせが多いのも、日本語に同音異義語が多いことが要因になっています。「この橋わたるべからず」という高札に対して「真ん中を通ってきました」という一休さんの頓智も橋と端という同音異義語を利用した「強弁」です。普通なら強引な解釈となるところが、頓智となるところが一休さんの偉・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
DINK
もう死語ですが、昔、Double Income No Kid 略してDINKというのが流行りました。夫婦で二人稼いで子供がいなければ豊かな生活ができる、ということなのです。この前提はそれまでは旦那さんの稼ぎだけで生活し、奥さんは子育てに追われて、子育てや教育には金がかかるので豊かな生活は送れない、という社会情勢があります。この思想が現在の少子化の原因であった、という指摘は未だにありません。そして夫・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハーブの日
8月2日はハーブの日です。ハーブ(herb)はアメリカ英語では「アーブ」と読むことを知っている日本人は稀です。このように発音しないhをsilent hといいます。他にもhonor, honestなど先頭に来るhを発音しない単語はあります。それぞれオナーとかオネストと読んでいるので、ホナーとかホネストと読む人は英語を習いたての小学生でもないかぎり、いないと思われます。日本でハーブと読むのはイギリス英・・・
- カテゴリー
- コラム Articles