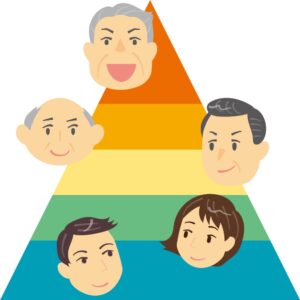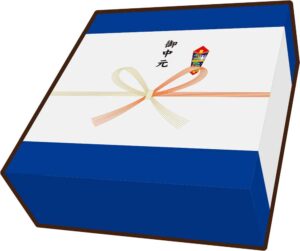その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
遣唐使
舒明天皇二年(630)葉月五日、第1回遣唐使が派遣されました。犬上御田鍬(いぬかみのみたすき)・薬師恵日(くすしのえにち)が派遣されました。二人の冠位は大仁(だいじん)ですから、上から三番目で後の正五位に相当するそうです。臣下ですが、そこそこ高位の人だといえます。聖徳太子が定めたとされる(異説あり)冠位十二階は徳・仁・礼・信・義・智にそれぞれ大小を付けたもので、大徳は希少ですから、今なら政務官とい・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
普遍主義
現在の経済や政治で話題になっているのがグローバリズムですが、その思想の根底にあるのが普遍主義universalismです。普遍主義の対立概念は個人主義individualismと解説する本が多いのですが、相対主義relativismと考える分野もあります。基本的な考え方として普遍主義はいろいろな事物の共通点を強調し統一的な原理によってそれらが支配されていると考えます。極端な考えとして、キリスト教や・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
北斗星君と道教
旧暦八月三日は北斗星君聖誕祭です。といってわかる方は相当な宗教オタクです。まず旧暦といっても中国の暦法なので日本の旧暦とは違いがあります。旧暦は別名太陽太陰暦で太陽と月の運行を基準として、それに季節を勘案しているので、ざっくりいうと中国と日本では緯度も経度も違うので若干の違いが生じます。日本の旧暦だと新暦8月29日で農歴でも同じですが、9月にお祭りすることもあるらしいです。 北斗星君は道教における・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
葉月二日、大雨時行
大雨時行(おおあめときどきふる)は大暑の末候、七十二侯の1つで、突然、夕立などの夏の激しい大雨が降る頃とされています。ゲリラ豪雨とか線状降水帯とか用語は時々で変わっても昔からこの時期には突然の大雨が降っていました。この時期の食べ物としては西瓜が旬とされていたのですが、今では時期が少しずれています。魚は太刀魚です。どちらかというと九州や四国が産地ですが、温暖化の影響で今はかなり北の方でもとれるようで・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
八朔
八朔といえばみかんを連想される方が多いと思います。八朔とは本来、八月朔日つまり八月一日のことです。八朔は特別な日でこの頃に早稲の穂が実るので、農民の間で初穂を恩人などに贈る風習が古くからありました。このことから田の実節句(たのみのせっく)という別名もあります。この「たのみ」を「頼み」にかけ、武家や公家の間でも、日頃お世話になっている(頼み合っている)人に、その恩を感謝する意味で贈り物をするようにな・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
修正終身雇用3 - ポスコロ5 -
農業から機械化へ、そして情報化へと産業の高次化が進化のようにとられられていますが、問題は産業の高次化が人間の生活に必要かどうかです。農業生産は今も必要で食べ物がなくなれば人類は死滅します。機械の鉄を食べるわけにはいきません。まして情報は食べようがありません。産業の発展は豊かさの本質ともいえる、飢餓がないこと、家族や世代が継続していくことで、産業の高次化はその豊かさと相反しています。実際、情報産業従・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
修正終身雇用2 ― ポスコロ4 ―
労働力は安いほど良い、という経営思想は正しいでしょうか。商品販売において、仕入れは安いほど良いという思想の経営者が多いですが、安かろう悪かろう、という商売が儲かっているとはかぎりません。安い労働力の極点は奴隷労働ですから、この思想は植民地主義と同じです。植民地主義の時代の生産力がどのようなものであったかは歴史が示しています。産業革命がなぜ起こったかを考えればわかることですが、奴隷労働に近い家内工業・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
修正終身雇用 ― ポスコロ3 ―
かつての日本の景気を支えた労働環境について、ポスト・コロナの今こそ、再考すべき制度がいくつもあります。その1つが終身雇用制度です。昔の労働者は定年までは雇用が保証されており、定年後は年金で暮らせるという安心感がありました。だからこそ、一生懸命勉強して、いい大学に入り、いい会社に就職するという夢があったわけです。ところが現在の環境はいつ解雇になるか不安であり、年金は開始年齢がどんどん遅くなり、しかも・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
処暑
文月二十六日は二十四節気の1つ処暑です。先日、立秋が過ぎたのにまた夏ですか、と思われる人も多いと思いますが、昔の人の季節感は秋だから涼しい、という感じではなかったのです。処暑とは「陽気とどまりて、初めて退きやまむとすれば也」つまり暑さもここらが峠で、これから徐々に退いていきます、という意味です。処というのは「お休み処」という看板を今でも見るようにトコロと読みますが、場所ということではなく、そこに居・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
普遍主義の終焉 ― ポスコロ2 ―
Covid-19は世界の国々の実情と文化に違いをくっきりと見せてくれる結果になりました。原因はまったく同じ疫病なのに、対応する政策とシステムが国ごとに違うことが明確になり、その根底には国民の思想と文化の違い、まさにその多様性が露呈しました。厳しいロックダウンの国が多い中、国民の自主性に任せる国は少数でした。日本では憲法云々という議論がありましたが、法を守るという遵法精神そのものが文化ですし、国民の・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
年功序列再考 ― ポスコロ ―
Covid-19の終息が見えてきて、世界はポスト・コロナの経済復興に舵を切っています。日本もあれこれ批判はあるものの、行動制限なしという政府方針はそのトレンドに乗るつもりです。制限がなくなるだけでは元に戻るだけですから、元の不景気に戻ったのでは意味がありません。これを好景気に転換できるような政策が必要です。賃金上昇が叫ばれますが、賃金が上がったところで儲かるのは所得税が増える財務省だけで、物価が上・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
地蔵盆
文月23日は地蔵盆です。関東地方ではあまり盛んではないのですが、関西地方では今でも盛んなようです。地蔵の縁日は毎月24日ですが、盆のある文月24日に地蔵盆が行われます。23日はその前夜、宵縁日で、本来はお盆同様、24日前後の3日間の行事です。普段の地蔵縁日は地蔵会(じぞうえ)といいます。 いわゆるお地蔵さんという地蔵菩薩の石像が昔は街角や村のはずれ、街道には必ずといっていいほどありましたが、今は寺・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
考証を考証する(2)
考証を英語にしようとすると、investigation調査、study勉強、evidence証拠、documentation文献調査といった語彙が出てきます。一語で置き換えられる訳語がなく、日本語の幅広さを示す語ですが、訳語のどの語彙にも共通する意味は事実をしっかり検証するということです。 ところが最近のテレビドラマの多くは、昔のモノクロ映画時代のように背景に重点がなく、ひどい場合はストーリーやセ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
考証を考証する
最近のテレビドラマを見ていると、考証不足が目につきます。アニメの方は聖地巡りがブームのこともあって、背景の実地検証とか時代考証などをかなりきちんとやっています。昔のアニメは製作上の制限もあって動かない背景とか適当な街並みを描くのが普通でした。なのでディズニーアニメで周囲の動物や植物が動くというリアリティに人手と時間をかけてきたことが感動を呼ぶ理由でもありました。初期の日本アニメは主人公の動きだけを・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
牧氏事件
元久二年(1205)閏文月二十日、幕府内で完全に孤立無援になった北条時政と牧の方は出家し、鎌倉から追放され伊豆国の北条へ隠居させられることになった事件です。 時政はその後、二度と政界に復帰することなく建保三年(1215)、北条の地で死去。牧の方も夫の死後は娘を頼って上洛し、京都で余生を過ごしました。北条氏の第2代執権には義時が就任して北条氏は幕府内における地位を確固たるものとなりました。 その前の・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
お盆と盆踊り
お盆に行うので盆踊り、というのは当たり前のことですが、案外単なる夏祭りだと思っている人が多いです。世界のどこにでも歌と踊りがあるのは共通ですが、日本の盆踊りには歴史があります。起源は鎌倉時代の踊り念仏だそうで、一遍上人が開祖である時宗(じしゅう)で広がったようで、今でも藤沢の遊行寺(箱根駅伝の途中に有名な坂があります)では全国から踊り念仏の人々が集まってきます。念仏とはナムアミダブツであり、他の念・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
中元
お中元として贈り物を送る人は多いのですが、その意味は意外に知られていません。中元とは昔の中国の道教の思想の1つ三元がもとになっています。三元というと今や三元豚とか麻雀の第三元しか思い浮かばないと思います。道教の三元とは上元、中元、下元のことで、それぞれ旧暦の1月15日、7月15日、10月15日になっています。三元の思想では三元は1年を3等分ではなく、2:1:1(6ヶ月・3ヶ月・3ヶ月)に分け、いず・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
江戸から東京へ
慶応四年、江戸が東京になりました。これは1本の明治天皇の詔勅「江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書(えどをしょうしてとうきょうとなすのしょうしょ)」によって決まりました。通称の「東京奠都の詔」という表現は、後年に至って用いられたものらしいです。内容は簡潔でwikipediaの現代語訳では以下のようになっています。 「私は、今政治に自ら裁決を下すこととなり、全ての民をいたわっている。江戸は東国で第一の大都市・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
一汁三菜
毎月13日は一汁三菜の日。夏はとくに栄養が偏りやすい時期なので、今月に話題として取り上げます。イチジュウサンの語呂合わせです。和食の基本なのですが、案外忘れられていると思われます。主食の御飯の他に汁物と主菜、副菜を2つという構成のことです。汁は味噌汁のことが多いと思いますが、とくに決まりはありません。主菜は伝統的には魚が多いですが、肉でもかまわないのです。副菜は煮物、酢の物が伝統的ですが、炒め物で・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ハイジの日
8月12日はハイジの日だそうです。例の語呂合わせですが、ということは完全に日本だけということでもあります。アニメ「アルプスの少女ハイジ」は童話を原作とした日本製のアニメですが、海外でも放送されたため、スイス製またはドイツ製と思われていることもあるそうです。20年ほど前にスイスに行った時には現地の人は誰も知りませんでした。それは2019年までスイスでは放送されていなかったからだそうで、アルム地方を通・・・
- カテゴリー
- コラム Articles