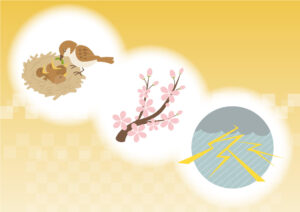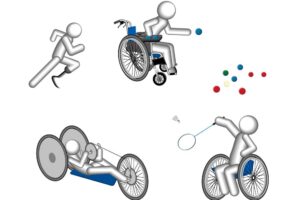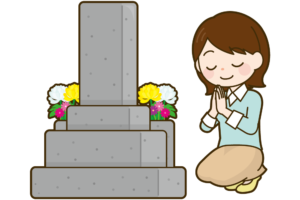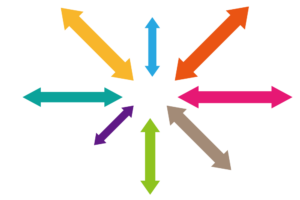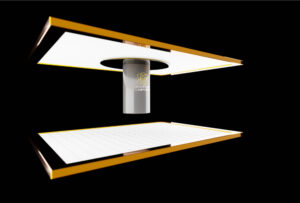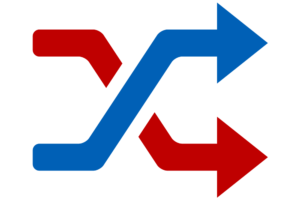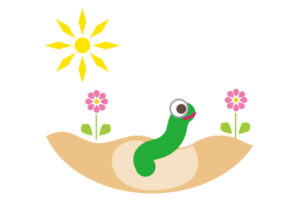その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
春分の日はなぜ休日?
3月20日は春分の日で休日です。外国人にこれを説明すると、一様に不思議そうな顔をします。春分の日は英語でvernal equinoxというのですが、vernalというラテン語は難しいので、spring equinoxという表現も増えてきています。欧米では、この日が春の最初の日という解説が多いようです。日本や中国では、節分や春節から始まると考えるのと、かなりのズレがあります。春分とは何かという科学的・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
日本の障害者福祉
外国人旅行者は点字ブロックに驚くのですが、実際、海外では見たことがありません。これは日本の福祉政策が世界でもトップクラスであることの証です。日本ではなぜか「日本の福祉は遅れている」と叫ぶ人が多いのですが、福祉は完全ということはまずありえなく、どこか足らないのが普通です。日本が遅れている、という主張をする人がよく比較するのが北欧ですが、北欧とひとまとめにいうことはできず、国ごとにそれぞれ政策は違って・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
点字ブロックの日
3月18日は社会福祉法人岡山県視覚障害者協会が制定した「点字ブロックの日」です。この日の目的は、点字ブロックの安全性確保と発展を図ることです。正式名称を「視覚障害者誘導用ブロック」といいます。点字ブロックは1965年に日本の長崎県で視覚障害者の教師である三宅精一氏によって考案されました。1967年3月18日に岡山県立岡山盲学校に近い国道250号原尾島交差点周辺(現:岡山県岡山市中区)に世界で初めて・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
春彼岸の入り
「暑さ寒さも彼岸まで」という諺があります。今年の彼岸の中日は20日ですが、もうその頃には冬のような寒い日はないと思われます。春の暖かさが実感される季節です。彼岸は昔からの伝統的行事ですが、太陽暦のため新暦でも同じ頃にやってきます。ちなみに3月20日は旧暦だとまだ2月11日でかなり早い彼岸ということになります。日の出は地域により多少の差がありますが、東京だと5:45ですから、実際の夜明けはもう少し早・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
文化のパラダイムシフト
政治経済や学問のパラダイムシフトだけでなく、社会制度の変更により社会生活も影響を受けることがあります。たとえば明治初期に日本は暦を変えました。新暦というのはキリスト教圏で使用されているグレゴリオ暦ですが、旧暦は長く伝統的に使用されてきた太陽太陰暦です。根本原理がまったく異なる暦法ですから、パラダイムシフトといえます。暦法の変更の動機は公務員の給料の支払いを減らすため、というまったく違った動機ですが・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
学問分野のパラダイムシフト2
学問のパラダイムシフトは基本原理の変更だけでなく、応用分野の変更につながります。近年話題になってきた量子コンピュータもその1つです。量子コンピュータの説明は難解なのですが、wikipedia では次のように説明しています。「いわゆる電気回路による従来の通常の2値方式のデジタルコンピュータ(以下「古典コンピュータ」)の素子は、情報について、なんらかの手段により「0か1」のような排他的な2値のいずれか・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
学問分野のパラダイムシフト
このところ相対論と普遍論についてご説明してきましたが、この対立する思想はあらゆる分野に影響しています。まず政治経済の世界でいえば、グローバリズムは普遍論が前提で、ナショナリズムあるいはローカリズムは相対論が前提となっています。世界でグローバルに展開する、ということは商品でいえば1つの商品に多少変化をつけながら、世界を相手に商売をすることです。現在のコンピュータのOSはマイクロソフトとアップル、グー・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
日本史と世界史
言語起源論のところでご説明した相対論と普遍論ですが、研究方法の深化と一般化とも根底の思想は同じです。言語研究に個別言語研究と一般言語研究があるように、歴史も個別の歴史学と一般的歴史学があります。日本史は前者、世界史が後者ということができます。しかし、現代の日本史はやや不思議な教育をしています。誰もが「いい国作る鎌倉幕府」のような年号覚えをします。いわば「常識化」していますが、これは西暦年号で、明ら・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
個別言語学と一般言語学
言語研究の方法には、特定の1つの言語だけを研究する分野と、広く複数の言語や人間の言語の一般性を研究する分野があります。前者が個別言語学あるいは特定言語学、後者を一般言語学といいます。わかりやすく言えば、前者の例が国語学、後者がいわゆる言語学です。 1つの分野を深く掘り下げていく研究方法を深化と呼んでいます。反対に広く一般性を追求する研究方法が一般化です。この2つは概念的には対立しているように見えま・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 語学
如月といえば
如月というのは普通に読むと意味がよくわからない名称です。ジョゲツならそのままですが、どう読んでもキサラギにはならない慣用的な読み方です。語源を見ると、「寒さで着物を更に重ねてきることから着更着という」とのが定説のようです。他にも気候が陽気になる季節なので「気更来」とか、「息更来」という説もあるようです。また更に草木が生え始めるので「木更木」という説もあるそうです。さらには芽が張り出す時期なので「草・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
旧歴如月朔日
旧暦では今日から如月です。昨年に閏月が入ったため、ほぼ1カ月遅れています。そのため二十四節気は太陽暦で動いていて、啓蟄が過ぎて、まもなく春分になる今頃になってから如月に入るという状態です。二十四節気は新暦とはほぼ一致しているので、天気予報などでも紹介されています。二十四節気は季節感を知る道標なのですが、その意味では、旧暦生活をしていると、「今年は季節が早くやってくる」ということになります。季節変化・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
実感と体感
実感も体感も脳の判断ですが、実感がメンタル(精神的)であるのに対し、体感はフィジカル(肉体的)な感覚であるところが異なります。体感は知覚から来るものなので、感情への影響はそれほど大きくないのですが、実感の方はメンタルなので、納得感のような感情に作用します。 日本語で考えるとなんとなく意味が似ているような感じがしますが、英語では名詞ではなく、動詞で表現することが多く、「実感する」はrealize、「・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 語学
ニュアンス
「私の表現のニュアンスがうまく伝わっていない」という経験は誰にもあると思います。この意味は「伝える側の意図」が受け手にうまく伝わっていない、ということで、メッセージの発信側の気持ちがニュアンスということになります。言い方を換えると、メッセージに込められた意図は発信側と受信側では違いがあるということになります。普段、この違いはあまり意識されることはなく、通信によるメッセージは「正しく」伝わるという前・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 語学
Spring is come.
Spring is come.と聞いて、「?」と思う人、懐かしいと思う人、「間違っている」と思う人、いろいろなのではないでしょうか。ある世代から上の人なら、昔の英文法の本にほぼ必ず載っていた「現在完了形の例外」として、「be+過去分詞」の例文になっていたので記憶の片隅にあるかもしれません。英語の現在完了形はhave + 過去分詞ですから、その例外になるわけですが、実際には日本語にないニュアンスがあ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
己巳の日
3月5日は旧暦だと「己巳(つちのとみ)の日」になり、60日に一度の金運の日です。似たような字が並ぶので、印象も強いかもしれません。干支は十干と十二支からできています。エトと読むのは兄(え)と弟(と)の組み合わせ、という意味で兄が陽、弟が陰であり、陰と陽、そして五行である木、火、土、金、水との組み合わせが10種類あります。木(き)に兄(陽)でキノエ、木に弟(陰)でキノト、というように、五行に陽と陰を・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
啓蟄
3月5日は二十四節気の1つ、啓蟄(けいちつ)です。天気予報では、ほぼどの番組でも二十四節気の話題をしますが、学校では教えていないと思います。旧暦だからでしょうが、太陽暦と関連しており、理科の勉強にもなりますし、国語や歴史や文化の勉強にもなるので教えてほしいです。 啓蟄とは、寒さが緩んで春の陽気になってきたことで、土の中から虫たちが動き出す季節のことを指します。「啓」はひらく、「蟄」は土の中で冬ごも・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
言語起源論4 言語学と宗教の関係
言語起源論のうち、言語普遍論は統一の祖先という思想であり、これはユダヤ教、キリスト教、イスラム教という唯一神を信仰する宗教の教義と一致します。ただし、インドはバラモン教から仏教、ヒンドゥ教へと変化してきても多神教なので、この思想とは一致しません。しかし唯一神を信仰する人々の間では、祖語があるということが人類共通の祖先となる語があるという思想と結びつきやすく、同時に言語は人間だけのものである、という・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
言語起源論3 と 比較言語学
言語起源論は哲学的問題もあります。むしろそちらの方が重要なのかもしれません。3月3日は「耳の日」ですが、とくに聴覚について考える日であり、聴覚の重要な機能である言語について考える日でもあります。そこで言語に対する2つの対立的概念について考えてみます。 言語学では昔から現在に至るまで、言語普遍論と言語相対論という対立する思想が支配しています。言語普遍論と名前はいかめしいですが、要するに人間の言語は1・・・
言語起源論2
言語起源論はオノマトペ説と身振り説に分けられる他、生得説と環境説に分けることができます。生得説というのは、言語は人間という種に固有に存在し、生まれながらにその学習機能が備わっている、あるいは本能だという考えです。それに対し、人間の言語習得は真っ白な状態から始まり、周囲から情報を習得することで発達していく、というのが環境説です。むろん、両極端ではなく、どちらの説も程度問題というか、言語データの重要性・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
言語起源論
ここ数年、言語学の世界で言語起源論が盛んになってきました。約百年位の周期で論争が起こります。昔の言語は文献以外の証拠がなく、文献発生以前の言語については明確な証拠がない推論のため、結論が出にくいのが最大の原因です。人類の歴史は化石という物理的な証拠があり、形態的な変化も測定できるので、進化過程も具体的に証明できます。化石の骨格から、喉の器官などの形状は推定できますが、音声そのものの痕跡はなく、あく・・・
- カテゴリー
- コラム Articles