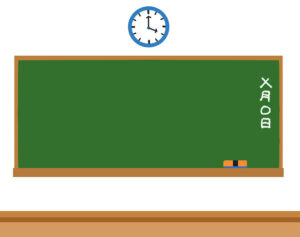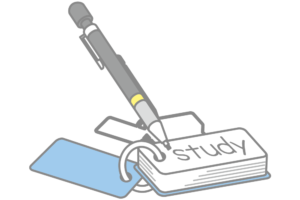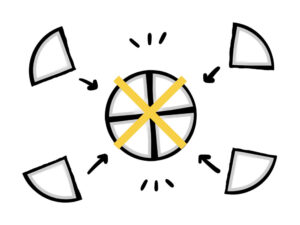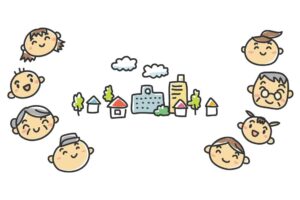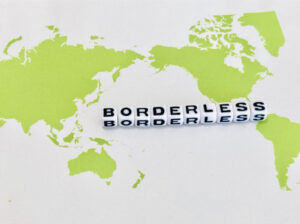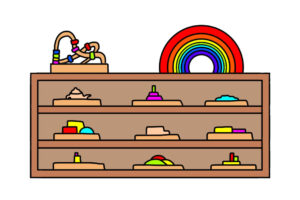その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
教師の時間的制約と教育費
教師は小学校から大学まで、授業時間という細切れの時間に支配されます。授業のほとんどは60分ですが、大学では未だに90分のところがほとんどです。なぜ90分なのか、という根拠はどうもはっきりしません。脳科学的に集中できる限界が90分という説明をしているところもありますが、この時間が始まったのもいつからなのか、はっきりしません。一方で文部科学省は大学設置基準で単位数を決める根拠を時間数に置いていて、「単・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
教師の話し方
アメリカなどでは、高校以上のカリキュラムに必須科目としてパブリック・スピーキングというのがあり、人前で意見を述べることの重要性が説かれ、実際の技術指導が行われます。公開の場で話をすることは、政治家の演説だけでなく、話すことを仕事としている職業、たとえばアナウンサー、法律家、ビジネスマンのプレゼンテーションなど、幅広く応用の聞く技術です。日本でも国語教育の1つとして教えてもよいはずです。しかし日本で・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
教師の姿勢と立ち居振る舞い
日本では教師は教壇の上に立つか、教壇がない場合でも、立って話すのが当たり前になっています。そのことに疑問をもつ先生はまずいないと思います。人前で大勢の人を相手に話をしようとすると、自然に立って話すのは人間の本能なのかもしれません。聴衆みんなから見えること、みんなが見渡せることにお互いに安心感があります。話す場合だけでなく、歌う場合でも同じことが起きます。お互いに「見える」ことが重要で、人間の認識が・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
教師の板書の効用
最近の小学校ではタブレットが使用されたり、電子黒板によって画像が提示されることが増えているそうです。先生はそのための準備が大変だそうですが、授業の準備が大変なことは昔と変わってはいません。画像を準備するのはかなり時間を要するので、提示時間が短い割に製作時間が長いのでタイムパフォーマンスはあまりよくありません。また提示時間が短く、次々と展開していくため、ノートを取ったり、考える時間がほとんどないため・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
教師の位置
教室における教師と生徒の位置関係は対面であるのが一般的です。先生が黒板の前に立ち、生徒は黒板に向かって座るというのは万国共通のようで、本能的にそれが一番わかりやすい方法なのかもしれません。しかし教室のない僻地などでは、木陰で先生が立って、あるいは座って本などを示し、生徒は固まって座って、それを見るというスタイルもみかけます。これは先生と生徒の関係は位置的には固定しているといえます。 塾の個別指導や・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
教師の目線
日本では教室の多くに教壇があります。小中学校ではほとんどなくなっていますが、大学ではまだ残っているところが多くあります。教育改革は下から上に波及していくため、古いシステムが大学に残滓が見られるわけです。教壇がなくても、先生は立って授業をし、生徒は座って聞くのが普通です。なぜなのか、と聞いても、「そういうものだから」というような曖昧な答えが返ってくるだけです。生徒の側から見ると、先生が見えるというこ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
弥生朔日
旧暦では本日から弥生になります。朔日(さくじつ)というのは「ついたち」という読み方もありますが、本来は満月日に対応する月が完全に欠けている状態を意味しています。これから次第に月が出てくるという意味で新月という呼び名もあります。これから毎日少しづつ月が増えていって、15日目に満月になる、という意味です。月の満ち欠けは晴れていれば毎日観測できますし、季節によって出る時間、入る時間も変わるので、それで一・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 季節
教師はガイド
欧米の教員養成課程を体験した日本人は少ないと思います。せっかく欧米に留学しながら、学んでくるのは教科書とかカリキュラムとか教育理論だけです。それは留学した人が教員であること、そして留学目的が新技術の習得が目的にあるためです。欧米の教員養成の講義では「教員はガイドである」ということが強調されます。この思想は日本人教師には受け入れがたいらしく、最初から興味がないとか、日本では通用しない、などとして排除・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
学習の動機
教える側(教師)にとって、教わる人(生徒)の学習動機はぜひとも知りたいことの1つです。ところが生徒の動機は案外マチマチで、どの生徒にも合うようなカリキュラムや指導法というのは存在しません。カリキュラムや指導法というのは平均的つまり数値上存在しても実際には存在しない仮定の理論です。生徒が学習した量というのは本来なかなか測定できないものなのですが、テストの点数によって数値化し、さらにそれを集めて統計的・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
記憶と忘却
インパクトの強いこととか、興味のあることは忘れないものです。しかし、そういう強い印象のあることはそう多くはありません。人間にかぎらず記憶量には制限があります。次々にやってくる記憶を留めておくには、不要なものを削除して余裕を空けるしかありません。脳はどうしても残しておかねばならないこと、たとえば命の危険の経験とか、楽しくてまた経験したいこと、などは記憶に残ります。それでも長い間には「いい思い出」に圧・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
学習の基本は反復
1度見たり聞いたりしたことは忘れない、という人はまずいないと思います。もしあるとしたらよほどインパクトの強い経験です。勉強や学習において、強烈なインパクトがあることはまずないといってよいでしょう。どちらかというと、退屈でつまらないことを覚えなくてはならない、ことがほとんどだと思います。教える側はどうにかして、おもしろくしよう、とか、楽しくしよう、とか工夫するのですが、実際にはそれほどおもしろくおも・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
清明
今年は4月4日が二十四節気の清明です。春分の次の節気で「万物が清々しく明るく美しいころ」とされています。自然がとくに美しい季節です。清浄明潔(しょうじょうめいけつ)という言葉の略だそうです。中国では清明節は祖先の墓に参り、草むしりをして墓を掃除する日であり、「掃墓節」とも呼ばれています。また、春を迎えて郊外を散策する日であり、「踏青節」とも呼ばれているそうです。アニメでも知られる『白蛇伝』では許仙・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
統一できないもの
統一できないものは意外にたくさんあります。たとえば言語です。為政者はいつも言語統一を図ろうとしてきましたが、うまくいかなかったことが歴史的に証明されています。現在の日本でも政府がNHKなどが「標準語」として統一しようとしてきましたが、結局は「共通語」として普及させたにすぎず、それも最近はかなりくずれてきています。NHKが定めた「標準アクセント」ですらアナウンサというプロでも、「正しくない」アクセン・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
統一が望まれるものと統一できないもの
なんでも「統一すべき」と考える人が多いのですが、実際には「統一が望まれるもの」と「統一できないもの」があり、「すべき」として強制すると無理が生じます。たとえば学年にしても、生徒がばらばらに入学してくると困るのは学校であり、生徒自身ではありません。小学生など1年の成長の差は大きく、4月生まれと3月生まれではかなり違いがあります。学習過程を考えると随時入学が適当であり、実際、音楽や美術などの習い事では・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
年度は統一すべきか
今日から日本は新年度に入ります。もう誰も疑問を抱きませんが、あれほど普段は欧米との比較を唱える人々が、この件についてはほとんど言及しないのは不思議です。実際、海外留学をした人にとって、半年間、損する制度です。大学によっては秋入学という制度をしている所もありますが、企業で秋就職制度をしている所はほぼないでしょう。企業がそれに従っているのは、新卒が4月から入社になるため、やむをえないためです。官庁で秋・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
プロセティック・ホリズム prosthetic holism
補綴を英語でprosthetics といいます。Holismは全体主義のことですから、直訳すると補綴全体主義となるのですが、その語から連想される内容はまったく違います。まず全体主義というと「個人の自由や権利を否定し、国家の利益や統制を最優先する思想や政治体制のことです。 全体主義は権威主義の極端な形態で、国家は人々の生活のすべてを管理し、独裁者やカリスマ的指導者によって支配されることが多いです。」・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
マス・ローカリズム
マス・ローカリズムという思想をごぞんじでしょうか。10年以上前にイギリスで主張が始まり、日本でもじわじわと広がりつつある社会思想です。マス・ローカリズムとは、地域社会から国家を再構築するビジョンと戦略に関する考え方です。「大規模・集中・グローバル」から「小規模・分散・ローカル」への転換を目指し、持続可能な地域社会づくりを推進することを目的としています。地域ごとの多様性を活かし、地域間での学び合いや・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
ボーダーレス社会
ボーダーレスとはborderless のことです。ボーダーは境界のことですが、多くの場合、国境を意味します。日本は海に囲まれているため、国境という意識が薄いとよくいわれます。同じ島国ですが、イギリスは陸の国境がアイルランドにありますし、そこがしょっちゅう紛争の原因になっています。またフィリピンは海の境界で中国と紛争があります。国境意識が薄いということは領土意識も希薄ということで、実際、時々政治的関・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
モンテソリ法を知ってますか?
モンテソリあるいはモンテッソーリと聞いて、すぐわかる人は教育関係者の一部だけでしょう。モンテソリ教育法は知的障害児へ感覚教育法を施し知的水準を上げるという効果があったことで有名になりました。1907年保育施設「子どもの家」を設立し、貧困層の健常児を対象に、その独特な教育法を完成させたという歴史があります。その成功が知られるようになって、欧米を中心に世界各国に広がりました。特にアメリカではモンテッソ・・・
- カテゴリー
- コラム Articles
- タグ
- 教育
大量生産から個別生産へ
これまでの産業の発達は、職人が1つ1つ手作りしていた時代から、機械工業へと変わり、大量生産によるコストダウンと大量消費が行われることにより、なされてきました。大量生産と大量消費という産業モデルには、コストダウンという大きな利益をもたらす要因があり、世界中で受け入れられてきましたし、今もその流れは続いています。 しかし大量消費には限界があり、物がない時代には何を作っても売れたのですが、ある程度、供給・・・
- カテゴリー
- コラム Articles