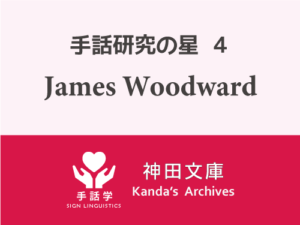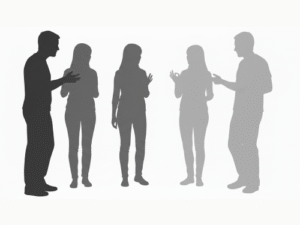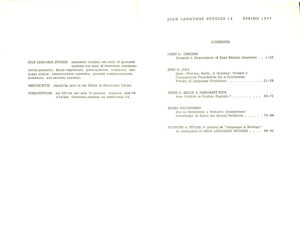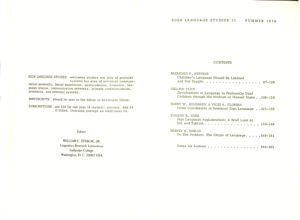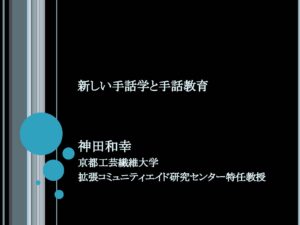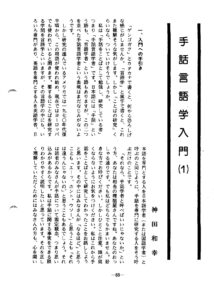その他の投稿も検索をすることができます。
「検索ワード」「分野」「内容」を入力して
「検索」をクリックして下さい。
手話研究の星5 マキンタイア(Marina McIntire)③ 新着!!
マリナの授業中の討論の中で、一人、日本にbuffaloがいるか?と質問してきた学生がいました。バッファローはアメリカの牛で、野牛であるバイソンbisonと並ぶアメリカ独自の牛という認識を持っていた私は日本にはいないと答えました。しかし彼は「いるはずだ、来週証拠写真を持ってくる」というので、次の週まで結論は持ち越しとなりました。 翌週、彼が持ってきた写真は沖縄の水牛の写真でした。これに対する答えはし・・・
手話研究の星5 マキンタイア(Marina McIntire)② 新着!!
そうした興味をもっていた一人がマリナ・マキンタイアでした。彼女は幼児の手話習得についての修士論文を出した直後で、当時は珍しいテーマであったため、私も興味を持ち講義にでることにしました。予想通り、学生は日米の手話の違いに興味を持っていましたが、それだけでなく、日本文化にも興味を持っていました。それはLAという特別な地域性もありました。日系人が多く住み、リトル・トーキョーという日本人街があり、日本から・・・
手話研究の星5 マキンタイア(Marina McIntire)① 新着!!
CSUNでの留学中の身分はAdjunct Professorでした。日本語に訳すと特任教授に近いですが、雇用契約は大学によって異なり、多くの場合、留学する客員教授や客員研究員にも使われる制度です。日本ではまずない制度ですが、アメリカでは通常7年間フルタイムの教授を務めると1年間の有給休暇の権利が与えられます。これをSabbatical leaveといいます。7年という周期には1週間と同じくキリスト・・・
手話研究の星4 ウッドワード(James Woodward)新着!!
カールのパーティで出会った一人に、スーザン・ディ・サンティスという女性の手話学者がいます。彼女は日本贔屓で、日本文化に深い興味があり、日本語も少し学習していました。日本文化に興味をもったのは、彼女がベジタリアン(菜食主義者)であり、日本食は最高だということでした。彼女は当時、LAの北のサンタバーバラの山奥に住んでいるということで、訪問することになりました。そのパートナーが“Woody”ウッドワード・・・
手話研究の星3 ルー・ファント(伝説の手話芸人)新着!!
カールの家では、世界の(といっても欧米限定ですが)祝祭日に、それに関する料理をしてパーティを開くということをしていました。パーティ好きの典型的アメリカ人ですが、そこにテーマがあるわけです。イースター、ハロウイン、クリスマスといった典型的なアメリカ文化はもちろん、北欧の文化、ユダヤの文化など、いろいろな文化と料理を同時に教わることができました。スージー夫人は料理名人で、レシピ本を見て、材料も仕入れ、・・・
手話研究の星1 カール・カーシュナー⑤(カリフォルニア聾学校)新着!!
当時、カリフォルニア州には2つの公立聾学校がありました。1つはサンバナディーノ、もう1つはフリーモントです。前々回のロイのコラム記事で、マージが所属していたオロニーカレッジの近くにフリーモント校があり、マージの紹介で視察できました。 ここの特徴は複数障害児の受け入れを積極的にしていたことです。当時のアメリカの聾学校は基本的に寄宿舎でした。遠くから通うことは無理だからです。そしてその小さなコミュニテ・・・
手話研究の星1 カール・カーシュナー④(Tripod とNPO)新着!!
TCという理念とインクルージョンという理念を合体させ、さらにモンテソリメソッドを導入した幼児教育を実践したのが、カールが創始したトライポッド(Tripod)です。トライは3、ポッドは足で、普通名詞ならカメラの三脚のことです。カールの思想は教師と親と子供の三者が同じ立場で尊重しあう、ということを三脚で象徴しています。 LAの北部に幼稚園を開設し、そこには聾児と聴児が同じ場所で学んでいました。手話は自・・・
手話研究の星2 ロイ・K・ホルコム(R.K.Holcom)新着!!
トータルコミュニケーションの創始者はホルコムという難聴者です。彼は私の英語でも聞き取れる中度難聴者で、夫人は聾者です。夫人も北カルフォルニアのオロニーカレッジの教授で、同校には日本からの留学生も多く、慕われています。ロイは夫人が聾者で、自分は難聴者で、3人の子供は聾者も難聴者もいます。3人とも優秀でホルコム三兄弟として活躍していました。 ロイによると、家族でコミュニケーションするには英語も手話も必・・・
手話研究の星1 カール・カーシュナー③(米教育制度)新着!!
手話と聾教育の実態を研究するには、全部回ってみるしかありません。そこでカールの紹介で、すべてを回ってみることにしました。日本からも何人かの研究者が訪問していますが、すべてを回って実態を調査するには、時間だけでなく面談するだけの英語力が必要です。訪問者のほとんどが、「見学」し、文献をもらって帰るだけでした。長期留学生は1か所だけです。私の場合は紹介者に恵まれたことも幸運でした。カールは実践家で社交的・・・
手話研究の星1 カール・カーシュナー②(米教育制度)新着!!
カール・カーシュナーがプリンシパルをしていたケンドールは、形式上ギャロデット大学に所属していますが、日本の大学付属校とはまったく違います。ケンドールは12年制という特殊な制度になっていて、その上にはモデル中等学校(MSSD)があります。ケンドールとMSSDは別組織のため、ケンドール卒業生は他の高校に行ったり、MSSDに他の聾学校から入学する生徒もいます。アメリカでは国民の多くが移動するため、生徒も・・・
手話研究の星1 カール・カーシュナー①新着!!
宗教関係のコラムはしばらくお休みして、今日から手話研究の星たちを筆者の実体験を元にご紹介いたします。研究業績については、論文をご覧いただくのがベストなので、ここでは人物についての私見を述べていくことで、研究者の実像と研究成果を比較していただき、その思想や文化的背景をご推察いただく資料としたいと思います。 第1弾はCarl Kirchnerです。来日も数回あるので、実際に会われた方、あるいはカリフォ・・・
聾教育と手話5
しかし、近年になって人工内耳の登場と普及が聾教育に影響を与えるようになりました。20世紀の終わり頃から、先進国では人工内耳が普及しはじめた。これに伴い、幼児期に人工内耳を装用した聴覚障害児の教育法が議論されるようになりました。人工内耳が登場した時期を中心として、多くの国において、聾者は障害者ではなく言語的少数者であると主張するグループから人工内耳装用は一種の民族浄化(少数民族としてのろう者の抹殺)・・・
聾教育と手話4
ドレペの設立したろう学校は、その後オーギュスト・ベビアンらによって手話法を更に進化させていきました。ベビアンは手話法に加えて書記言語の必要性を指摘し、一方で口話や読話は重視しませんでした。こうしたことから、ベビアンはバイリンガルろう教育の元祖と見なされることもあります。ドレペの手話法は19世に入るとトーマス・ホプキンス・ギャローデットによってアメリカ合衆国にも普及しました。また19世紀ヨーロッパで・・・
聾教育と手話3
昔の聾教育の具体的な内容は、史料が存在しないためわからない状況ですが、現在のスペインや南フランス、イタリアなどの地域の修道院では13世紀頃から各種の指文字が使用されていたことがわかっており、それらを用いてろう教育を行ったのではないかと考えられています。16世紀のスペイン、レオン地方に住んだベネディクト会の修道士ペドロ・ポンセ・デ・レオンが1570年頃、4人の聾児(いずれも貴族の子弟)に墨字と指文字・・・
聾教育と手話2
聾教育を創始したのは、フランスのドレぺ神父(1712年11月24日 - 1789年12月23日)による1760年である、とされています。またドイツのハイニッケが1778年に聾学校を開設しています。日本の聾教育の創始は古河 太四郎(ふるかわ たしろう)(1845年4月26日)- 1907年12月26日)により1878年とされていて、120年ほどの差があります。当然、古河には西洋の実情に対する知識はあ・・・
聾教育と手話1
ここで、しばらく手話学から離れて、聾学校と手話の関係についての基本知識を学びましょう。 聾学校と手話の関係は時代と共に変化しました。世界のすべての聾教育は手話から始められました。聾者が「身振り」をすることは昔から知られており、その身振りで、周囲の人とある程度のコミュニケーションができていました。現在、手話と呼ばれているものは、昔の日本では「手真似」と呼ばれていました。現在では「手話は言語」という考・・・
Sign Language Studies 14
書名 Sign Language Studies 14 概要 手話と生物学の関係のみならず、視野を広げて、性教育や性用語の通訳についても言及するWoodwardの論文が載っている。1977年当時、すでにgayやlesbianなどによる分類があり、差別について厳しい論評をする彼の視点がわかる。現在話題のLGBTは昔から米国では差別の対象であった。ただこの時点ではTやQ、Aについては意識になかったよう・・・
Sign Language Studies 11
書名 Sign Language Studies 11 概要 手話と聾児との関係や手話の言語習得に関する論文が集められている。アメリカ手話の場合だけでなくトルコのケースも言及されている。また言語起源論も掲載されている。手話研究の視野が広がってきた傾向を示す号である。 "
新しい手話学と手話教育(PDF版)
動画 PowerPointによる発表済の手話の工学的研究についての提案のPDFのみの公開。動画は別途発表。音響工学との比較による手話工学の構築案を具体的に示した。手話の構成素は手の形、位置、動きという定説を工学的に見直し、動作とCLという要素を考え、動作は位置と動きを合成した軌跡とし、手の形は手話動詞の語幹になるという定義をすることで、新しい手話学を提案した。
手話言語学入門(連載記事)
解説 本書は1985年から3年にわたり、全日本ろうあ連盟の季刊誌から依頼を受けて連載したものです。期間が長いため、書いている間に多少概念の揺れなどがありますが、基本的には言語学の立場から見た手話という言語についての私論が展開されていますので、現在でも通用する箇所が多いと思います。また専門書ではなく一般向けですので、比較的わかりやすいと思います。当時はまだ手話を言語と認めない人が多く、とくに聾教育界・・・